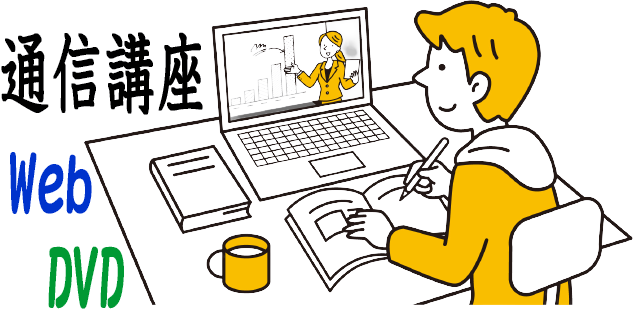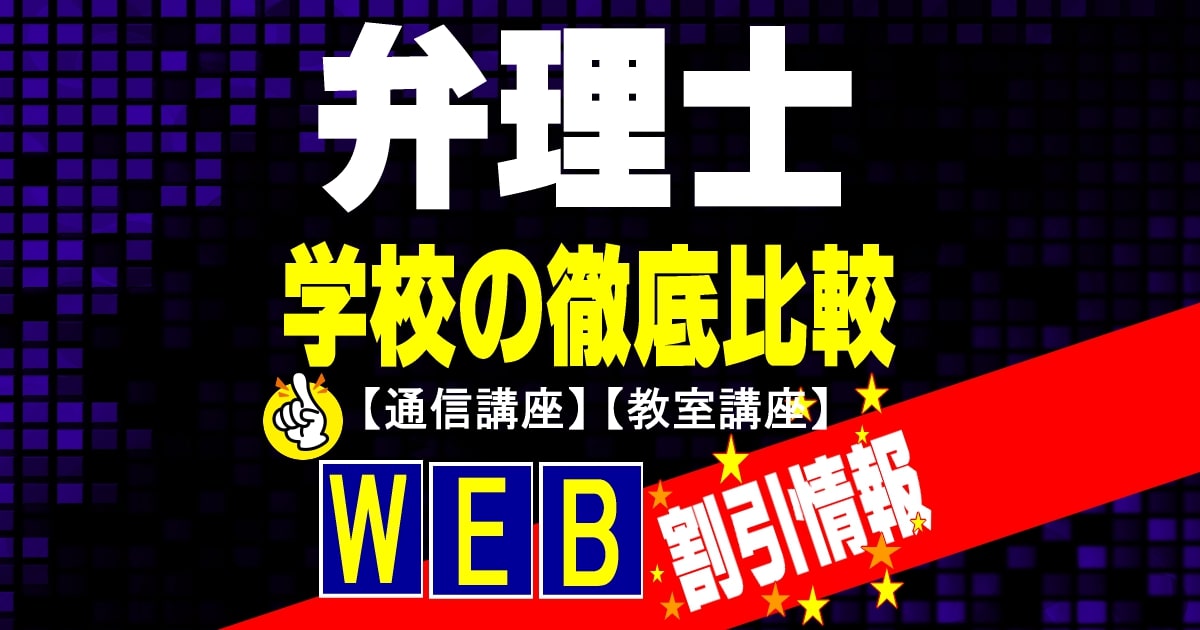このページでは「弁理士の学校・予備校」を比較し、読者の皆さまにおすすめの情報をご提供いたします。弁理士の学校を選択するメリットは、最短で弁理士試験合格に近づくことです。
特に、オンライン通信講座がある学校は、自宅や会社、通勤中、ワーキングスペースなどで、好きな時間に好きなタイミングで受講できます。さらに、模擬試験受験など必要に応じて教室で受講できるサービスを提供している学校もありますので、弁護士試験の緊張感を体験することができます。
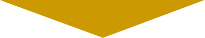
- 教材のクオリティの高さが評判のオンライン通信講座ならアガルート
- 受講料は安めで人気のオンライン通信講座ならスタディング
- 通学講座で効率的な教材で合格実績を積み上げているのがLEC(東京リーガルマインド)
おすすめの弁理士の学校・予備校5選を徹底比較

弁理士の学校・予備校の比較
弁理士の学校・予備校を選択する際には、下記の項目に注意して選びましょう。
- 弁理士の学校・予備校のランキングは通信か通学かで大きく分かれる。
- 弁理士の学校・予備校をテキスト・講師・カリキュラムで比較する。
- 弁理士の学校・予備校の評判・口コミを確認する。
- 弁理士の学校・予備校の費用を比較する。
以上を基本としながら、2023年11月最新版の弁理士試験の人気予備校の比較・評判の他独学におすすめのテキストや勉強方法もご紹介します。
上記項目を満たしているおすすめの弁理士の学校・予備校ランキングは次の通りです。
弁理士の学校は、①オンラインWeb通信教育・独学向きの学校・予備校 ②通学講座の学校・予備校とに大きく分かれます。それぞれ、弁理士受験生向けの学校(受験予備校・専門学校)の当サイトおすすめランキングとなっています。
アガルート、スタディングなどの弁理士講座はオンラインWeb通信講座に特化することで、講座費用が低価格の設定となっております。そのため、仕事で忙しい社会人など独学で勉強する人にもおすすめです。
資格の学校TAC、LEC(東京リーガルマインド)などの通学・通信の学校は、長年の指導実績・多くの合格実績という安心感があります。社会人にもおすすめの弁理士試験向け朝クラス、昼クラス、夜間クラスの通学講座も開設されています。(学校・校舎によります。)
以上を踏まえ、弁理士の学校・予備校を簡潔に比較した表は下記の通りです。
| 学校・予備校 | Web通信講座 | 通学講座 | セット内容(例) | 受講料(例) | 対象者 |
|---|---|---|---|---|---|
| アガルート | 〇 | ✕ | ・総合講義 ・論証集の使い方 ・重要問題習得講座 ・短答知識完成講座 | 【2025年合格目標】 総合カリキュラム 218,000円 | 初学者 経験者 |
| スタディング | 〇 | ✕ | ・基礎/短答講座 ・インプット学習 ・論文問題演習 ・実力答練 | 基礎・短答・論文総合コース:88,000円 ・基礎・短答合格コース:59,400円 | 初学者 |
| 資格スクエア | 〇 | ✕ | ・基礎 ・短答 ・論文パック | 25年度合格:297,000円 | 初学者 |
| LEC | 〇 | 〇 | ・基礎講座 ・短答解法修得講座 ・論文書き方講座 ・短答試験 ・論文試験 ・口述試験 ・アウトプット学習 | 短答&論文速修コース ・通信講座Web+音声DL:435,000円 ・通学口座Web+音声DLフォロー付き465,000円 短答コンプリートコース ・通信講座Web+音声DL:365,000円 ・通学口座Web+音声DLフォロー付き:385,000円 ・通信講座短答総仕上げゼミ付き:408,000円 1年合格ベーシックコース ・通信講座Web+音声DL:495,000円 ・通信講座DVD:549,000円 ・通信講座+提携校通学Web+音声DL+通学:539,000円 ・通信講座+提携校通学DVD+通学:593,000円 1年合格ベーシックコースWIDE ・通信講座Web+音声DL:545,000円 ・通信講座DVD:599,000円 ・通信講座+提携校通学Web+音声DL+通学:589,000円 ・通信講座+提携校通学DVD+通学:633,000円 | 初学者 経験者 |
| 資格の学校TAC | 〇 | 〇 | ・Basic講義 ・基本講義 ・実力テスト ・法改正セミナー ・実力完成答練 ・全国模試 ・総合答練 | 1.5年本科生 ・教室講座 Webフォロー付:352,000円 ・Web通信講座:352,000円 8ヵ月本科生 ・教室講座 Webフォロー付:308,000円 ・Web通信講座:308,000円 上級本科生 ・Web通信講座:440,000円 | 初学者 経験者 |
それでは、各学校のサービスを詳しく解説していきます。
オンラインWeb通信講座ランキング
まず、自宅の他のカフェ、通勤時間などスキマ時間を利用して学習しやすいオンラインWEB通信講座を中心に開講している学校・予備校のサービスから解説していきます。
ランキング1位 アガルート 弁理士講座

| 学校名 | アガルートアカデミー | 特徴 | ・160時間の講義時間と情報が網羅されたテキストがついて低価格 ・出題カバー率選択式93.8%・択一式91.4%で合格に必要な知識をインプットできる ・疑問に思ったことは回数無制限の質問制度で解決 ・月に一回のホームルーム動画配信 ・(オプション)定期カウンセリングで講師が一人ひとりをフォロー |
| 受講形態 | オンラインWEB通信 | メリット | ・最小限の講義で実力が身につくよう絞り込まれた講座体系 ・フルカラーのテキストが読みやすく、頭に残りやすい ・わかりやすい講義動画、倍速機能、音声ダウンロード等で時間と場所を選ばず学習できる |
| 対象者 | 初学者・経験者 | 配信スタイル | アガルートの講義動画は、PC、スマートフォン、タブレットが使用できる「マルチデバイス対応」となっており、WindowsもMacOSも更にブラウザすら選ばず視聴できる。 |
| 開講講座 | 【2025年合格目標】 総合カリキュラム 218,000円 | 合格特典 | ・受講料全額返金+お祝い金3万円プレゼント |
アガルート弁理士講座は、WEB学習に最適化された講義動画を中心としたオンラインWeb通信講座です。アガルートは、「最小限に絞った講座体系」×「最良のテキスト」×「使いやすい受講環境」による「徹底的な合理化」を追求する姿勢で、短時間で濃密に学習し合格に最短距離で向かうことができるような学習環境が提供されています。
※アガルート 弁理士講座は、令和4年度の本試験合格率6.1%に対しアガルート受験生の合格率が40.91%と圧倒的な合格率の高さを実現しています。アガルート弁理士講座の圧倒的な合格率は、3年で受講者数が約5倍となるほど高い評判を呼んでいます。
- 160時間の講義時間と情報が網羅されたテキストがついて低価格
過去の試験で出た情報が網羅されており、社労士試験の合格に必要な情報がすべて詰まっています。また、事項検索が付いているため検索に便利。疑問点が出てもテキストに立ち戻って調べることで解消しながら進めていけます。 - 出題カバー率選択式93.8%・択一式91.4%で合格に必要な知識をインプットできる
総合講義における令和3年度試験の出題カバー率は選択式93.8%・択一式91.4%です。例年7割程度の得点で合格できることを考慮すると、総合テキストの内容が理解できていれば十分合格可能です! - 疑問に思ったことは回数無制限の質問制度で解決
講師自身が質問に答えてくれます。講師としっかりコミュニケーションのはアガルート特長です。 - 月に一回のホームルーム動画配信
受講生からのアンケート(勉強方法と学習内容)をベースに、講師が毎月ホームルーム動画を配信しています。講師とコミュニケーションが取れ、悩みを解消してくれるとともに直近の弁理士関係の話題も届けてくれます。 - オプション)定期カウンセリングで講師が一人ひとりをフォロー
定期カウンセリングでは、講師による電話で毎月1回30分程度のカウンセリングが受けられます。学習の進捗状況の確認・疑問点の解消等一人ひとりの状況に合わせたフォローが受けられます。
\ アガルート 弁理士講座では、様々な割引や合格特典が用意されています/
※サンプル教材・e-ラーニング無料試用版などの特典があります
ランキング2位 スタディング弁理士講座

| 学校名 | スタディング | 特徴 | ・スキマ時間で学べる ・初心者でもわかりやすいビデオ/音声講座 ・無理なく実力をつけられるアウトプット学習 (スマート問題集・実戦力UPテスト・検定対策模試) ・圧倒的な低価格 |
| 受講形態 | オンラインWEB通信 | メリット | ・効率的に合格するための工夫あり! ・早く基本的な内容をインプット ・問題や過去問を使ってアウトプット練習 ・AIなどを駆使した効率がアップする学習システム |
| 対象者 | 初学者・経験者 | 配信スタイル | 【基本講座】動画+Webテキスト:通常速・1.5倍速・2倍速 【スマート問題集】オンライン問題集 【トレーニング】PDF問題集 【実力テスト】【検定対策答練】【模擬試験】PDF問題+動画 【ガイダンス】【解答力UP講義】動画 |
| 開講講座 | 基礎・短答・論文総合コース:88,000円 ・基礎・短答合格コース:59,400円 | 合格特典 | ・2024年+2025年度版コース好評販売中 11,000円OFFキャンペーン実施中【10/31(火)まで】 合格お祝い金10,000円付き! |
※スタディング弁理士講座の動画講義は、「試験によく出る」「書籍では分かりにくい」ところを重点的に扱い、1本5分~15分程度の動画にまとまっているため、効率よくインプット学習が進みます。動画講座を活用することで、移動中でも手軽に学習できます。再生速度も、通常速、1.5倍速、2倍速などに調節でき、慣れてきたら倍速など、自分の理解度に合わせた学習が可能です。
- 復習スケジュール
人は一度覚えたことでも時間が経つと忘れてしまうものです。 問題を解いた履歴から理解度を集計し、 最適な復習スケジュールが組み立てられます。間違えた問題は短い間隔で出題されるので苦手な問題でも覚えることができます。 - 復習問題を自動的にピックアップ
AI問題復習機能を開けば「今日復習すべき問題」がお知らせされます。復習する問題探しも計画もAIにおまかせできるので 試験までの限られた時間の中でも効率よく力がつきます。
大手資格学校で長年経験のある講師経験のある講師陣による講義!
弁理士試験難しさに挫折してしまう受験生が多くいますが、完璧でなくとも先へ足を進めることこそ合格のために大事なことです。なので途中で挫けることなく、着実にステップアップしてほしいという思いを込めて、スタディング弁理士講座の教材は、基本講義、スマート問題集、トレーニング、実力テストと、一段ずつステップアップできるような難易度で開発されています。
\ 弁理士講座では、無料でオンライン講座が体験できます/
※サンプル教材・e-ラーニング無料試用版などの特典があります
ランキング3位 資格スクエア弁理士講座

| 学校名 | 資格スクエア | おすすめポイント | オリジナルカラーテキスト ・基礎知識定着のためのワークシート ・論文答案作成に必要な能力を養成する練習問題 ・科目別論文テキスト |
| 受講形態 | オンラインWEB通信 | メリット | ・合格者に学習相談 ・学習可視化でモチベ維持 ・模試で実力確認 |
| 対象者 | 初学者・経験者 | 配信スタイル | 全テキスト製本版付 |
| 開講講座 | 297,000円(税込) | 割引情報 | 乗換割(20%オフ)・再受講割(50%オフ) ほか |
資格によっては、AI(人工知能)による予想問題を作成するなど、他の通学型の予備校や通信講座との違いを前面に押し出しており、昨今大変注目されている学校の一つです。資格スクエアは、学校・学習塾・個人学習で使える国内・世界のEdTechの最新動向等を広く情報発信することが目的の経済産業省のサイト「未来の教室」にも掲載された注目の受験校です。
※
- AIが予想する短答式試験模試!
AIが当該年度の出題傾向を予測し過去問をセレクトする「未来問」。
実際の試験時間に即した模擬試験形式の模試がオンラインで無料で受けられます - 口述模試
本番を意識した問題と、丁寧なフォロー、的確なフィードバック。
オンラインで受講でき、受験生からも大好評の口述模試が、論文合格時は無料で受けられます。 - 講師による基礎講義をはじめ質の高い講義
満足度97.7%を誇る高野講師の基礎講義が法律の扉を開きます。
そして資格スクエアの講義の特徴は、「予備試験合格に必要なこと」に焦点を絞ったコンパクト設計。講義聴講に時間をかけすぎることを防ぎ、アウトプットに時間をかけられるようにしています
\ 資格スクエア 弁理士講座では、まずは無料の資料請求/
※サンプル教材・e-ラーニング無料試用版などの特典があります
ランキング1位 LEC(東京リーガルマインド) 弁理士講座

| 学校名 | LEC(東京リーガルマインド) | おすすめポイント | ・業界屈指の充実のテキスト ・合格へ導く実力の講師陣 ・高い本試験的中実績 |
| 受講形態 | 通学・通信講座 | メリット | ・通学コースは講義Web動画+音声ダウンロード又はDVD動画が受講料込みで標準装備なので、欠席時や復習に活用できる ・複数講師の講義動画が視聴可能で、自分に合った講師を選べる ・さらにZoom講義も利用できる ・コース生限定の一般常識メルマガで一般常識を少しずつ学習できる ・「教えてチューター」制度で、わからないところをメールで質問可能 ・「テレホンチューター」で講師に電話で相談できる ・もちろん講師に直接質問できる |
| 対象者 | 初学者・経験者 | 配信スタイル | ・WEB通信+音声ダウンロード ・DVD通信 |
| 初学者対象コース (主なもの) | 短答&論文速修コース ・通信講座Web+音声DL:435,000円 ・通学口座Web+音声DLフォロー付き465,000円 短答コンプリートコース ・通信講座Web+音声DL:365,000円 ・通学口座Web+音声DLフォロー付き:385,000円 ・通信講座短答総仕上げゼミ付き:408,000円 | 経験者対象コース (主なもの) | 1年合格ベーシックコース ・通信講座Web+音声DL:495,000円 ・通信講座DVD:549,000円 ・通信講座+提携校通学Web+音声DL+通学:539,000円 ・通信講座+提携校通学DVD+通学:593,000円 1年合格ベーシックコースWIDE ・通信講座Web+音声DL:545,000円 ・通信講座DVD:599,000円 ・通信講座+提携校通学Web+音声DL+通学:589,000円 ・通信講座+提携校通学DVD+通学:633,000円 |
LEC(東京リーガルマインド) 弁理士講座は、教室での講義をメインとしながらWebやVTRでの通信講義も活用した通学・通信講座です。LEC(東京リーガルマインド)では、わかりやすいだけでなく学習を効率化するための講師・教材を提供しています。
※講師を複数人から選べる制度はLEC弁理士講座ならではの特徴となっています。科目ごとに自分に合った講師を選べます。また、複数の講師の講義を受講することで同一論点を違う角度から学習でき、理解度をより深められます。
LECの3つの特徴
- 業界屈指の充実のテキスト
社労士試験合格に必要な知識を、わかりやすくインプット、徹底的なアウトプットで、解答力を鍛えられます。 - 合格へ導く実力の講師陣
長年の実績と蓄積された情報とノウハウを駆使し、合格までの最短距離をLEC講師陣がナビゲートしてくれます。 - 高い本試験的中実績
LECの教材は本試験問題への的中率が高いです。弁理士本試験の的中実績は、は公式サイトで公表されています。
\ LEC(東京リーガルマインド) 弁理士講座公式サイトではおためしWeb受講ができます/
※割引情報・クーポンなどが入っている場合があります
ランキング2位 資格の学校TAC 弁理士講座

| 学校名 | 資格の学校TAC | おすすめポイント | ・クラス担任制の優秀な講師陣 ・初学者と上級者レベル別のオリジナル教材 ・段階的に実力がつく戦略的カリキュラム ・受験生の多様なニーズに対応する学習メディア ・安心のフォローシステム |
| 受講形態 | 通学・通信講座 | メリット | ・全国各地の空き教室を利用した無料の自習室が利用できる ・授業に欠席しても他のクラスに自由に振り替えて出席することが可能 ・講師に直接・電話・メールで質問でき、疑問点はすぐ解決できる |
| 対象者 | 初学者・経験者 | 配信スタイル | ・通学スタイルでは教室講座、ビデオブース講座を選択可能 ・スマホ、タブレット、PCで講義動画を繰返し視聴可能。 動画、音声ともにダウンロードもできる。テキストもデジタル版で提供 |
| 初学者対象コース (主なもの) | 1.5年本科生 ・教室講座 Webフォロー付:352,000円 ・Web通信講座:352,000円 8ヵ月本科生 ・教室講座 Webフォロー付:308,000円 ・Web通信講座:308,000円 | 経験者対象コース (主なもの) | 上級本科生 ・Web通信講座:440,000円 |
資格の学校TAC 弁理士講座は、教室で講師による生講義で白熱した環境で学習でき、かつWeb通信講義もできる通学・通信講座です。長年の試験研究から作り上げられ、今も進化し続けている教材こそが資格の学校TACの強みです。
※資格の学校TACの弁理士講座では、長年の指導ノウハウを活かした無駄のない教材・カリキュラムを提供しており、忙しい学生や社会人でも学習を両立できるようになっています。2011年からのTAC本科生の合格者累計実績は5,195名と多数の合格者を輩出している実績があります。
資格の学校TACの5つの特徴
- クラス担任制の優秀な講師陣
資格の学校TACは「クラス担任制」。講師と受講生との「顔の見える関係」を重視し、長い学習期間を最後まで熱い講義でサポートしてくれます。 - 初学者と上級者レベル別のオリジナル教材
資格の学校TACの教材は試験傾向を徹底的に分析して毎年改訂されています。初学者も無理なく理解できるよう、随所に工夫がされており、INPUTから過去問・答練などのOUTPUTに至るまで、合格に必要な教材は全て含まれているので、安心して学習できます。 - 段階的に実力がつく戦略的カリキュラム
資格の学校TACのカリキュラムは、合格に必要な要素のみが効率的に配置されています。TACのカリキュラムに沿って学習すれば、自然と合格レベルへの到達できます。 - 受験生の多様なニーズに対応する学習メディア
資格の学校TACでは全5種類の受講形態を用意。教室講座、オンラインWeb通信講座、DVD通信講座なども用意されています。 - 安心のフォローシステム
欠席した時には他のクラスに自由に振り替えて出席できるクラス振替出席フォローや、学習上の疑問を解消できる質問メール制度が用意され、忙しい方でも安心です。
通学講座
- 特徴:決まった日程・時間に資格の学校TACに通学し、教室で講義を受ける学習スタイルです。講師と受講生との「顔の見える関係」を重視し、長い学習期間を最後まで熱い講義でサポートしてくれます。欠席フォローや振替出席制度などのサポートも充実しています。
- メリット:①専任講師と実務家講師の連携による高い講師力 ②不明点も即解消できる質問受付。さらに教室にいなくても電話・メールでの質問対応可能 ③通学することで学習ペースを一定に保てる ④安心の欠席フォロー
オンラインWEB通信講座
- 特徴:PC・タブレット端末・スマートフォンを使っていつでもどこでも資格の学校TACの講義が受講できます。講義動画・音声はダウンロード可能なので、通信料を気にせず外出先でもスキマ時間に学習可能。校舎が遠くて通学できない方、通学の往復時間がもったいないと感じる方でも手軽にTACの授業が受けられます。
- メリット:①Web講義・音声講義でいつでもどこでも繰返し講義を受けられる ②Web講義動画・音声はダウンロード可能で通信料や通信環境を気にしなくてOK ③スピード再生機能で効率的に学習できる ④パソコンだけでなくスマートフォン・タブレット端末でも視聴でき、スキマ時間での学習が可能 ⑤質問も電話・メールでできる
\資格の学校TAC 弁理士講座について詳しく知りたい方は、まずは無料の資料請求!/
※割引情報・キャンペーン情報などが入っている場合があります
【合格極意】これから弁理士試験を目指す人に4STEPで解説!

- 弁理士試験に短期間で受かるおすすめの方法は?
- 独学・通信・通学の学校の比較~私に合っている弁理士の学校は?
- 少しでも費用を安く抑えて弁理士試験の勉強をするには?
- 弁理士の学校の口コミ・評判を確認するには?
弁理士試験の勉強をするにあたり、独学・通信の学校・通学の学校のそれぞれメリット・デメリットを挙げた上で、オススメできる選択肢をランキング形式で解説します。
- メリット
- 通学にかかる移動時間を省略できるため、忙しい人には向いている!
- 講義動画が短く区切られているため、スキマ時間で学習できる!
- 通学の学校に比べて受講費用が安いことが多い!
- デメリット
- 学習スケジュールが定まっていないため、自分でスケジューリングと進捗を管理しないといけない
- 勉強仲間ができにくいため、自分のレベルの確認やモチベーションの維持が難しい
- メリット
- カリキュラムごとに講義日程が組まれているため、学習計画の作成や進捗管理が不要
- 他の受講生がいることや勉強仲間が作れることで、モチベーションを維持しやすい
- デメリット
- 通学に時間がかかる
- 講義時間が長いためまとまった時間が必要
- メリット
- 教材のみを買えばよいので、費用が安い!
- 好きな時間で勉強を開始・終了できる
- デメリット
- 教材の品質の判断基準が乏しいため、良質な教材を見極められない
- 問題の重要度を判別できないため、学習が非効率になりがち
- 学習ペースの管理の難しさ、テストなどの目標がないこと、勉強仲間の不在などから、モチベーションを保つのがかなり難しい
弁理士試験の学校を利用する場合も独学の場合も試験勉強には費用がかかります。そこで費用をなるべく抑える方法を解説します。
- 弁理士の学校を利用する方
- 教育訓練給付金の給付対象講座を受講する
- 学校が実施するキャンペーン期間に申込する
- 学校の公式サイトで発行される割引クーポンを利用する
- 独学の方
- 実力チェックは学校の実施する模試を利用する
- どうしても学習が難しい箇所のみ学校の単科講座を利用する
学校の公式サイト・パンフレットの他、生の口コミが聞けるのはTwitter・FacebookなどのSNSです。
下記に主な口コミ・評判を掲載しました。
弁理士の試験ガイド
「弁理士試験」の概要をご紹介します。
- 受験資格
- 受験申込期間
- 試験日程
- 試験内容
- 受験地
- 合格発表

※なお、2020年より新型コロナウイルスの影響等により、各日程が変更となる可能性があります。最新情報は、試験の公式ホームページや願書等によりご確認ください。
願書配布
3月上旬~4月上旬(インターネット請求は2月上旬~3月下旬)
願書受付
4月上旬
受験料
12,000円(特許印紙にて納付)
弁理士試験に関するお問い合わせ先
- 工業所有権審議会
弁理士審査分科会事務局(特許庁総務部秘書課弁理士室試験第一班)
TEL:03-3581-1101(内線2020)
特許庁ホームページ
実務修習に関するお問い合わせ先
- 指定修習期間 日本弁理士会
TEL:03-3581-1211(代表)
日本弁理士会ホームページ
弁理士試験詳細
1. 1次試験 短答式筆記試験(正確な知識を問われる試験)
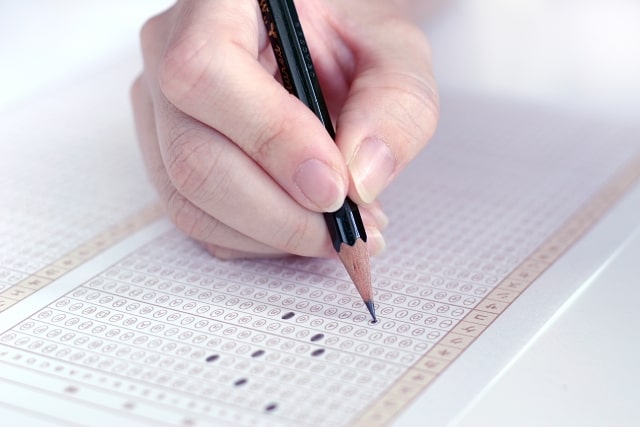
短答式筆記試験は、弁理士活動を行うにあたり必要な基礎的知識を有するか否かを判定するため、その基礎的知識、条文の解釈及び正確な理解を問う、5肢択一のマークシート形式の試験です。
- 受験資格
特になし。どなたでも受験することができます。 - 試験日
5月中旬~下旬(願書受付は4月上旬) - 試験地
東京、大阪、仙台、名古屋、福岡 - 合格発表
6月上旬~中旬 - 免除対象者
免除制度の詳細につきましては、特許庁ホームページをご覧ください。 - 試験概要
- 試験形式 5肢択一:マークシート方式
- 試験科目 特許・実用新案に関する法令(20題)、意匠に関する法令(10題)、商標に関する法令(10題)、工業所有権に関する条約(10題)、著作権法及び不正競争防止法(10題)
- 出題数 全60題
- 試験時間 3時間半
- 合格基準 以下のすべてを満たすこと
- 試験科目別の合格基準(各科目40%を原則※注1)を満たす得点であること
- 満点に対して65%の得点を基準として、論文式筆記試験及び口述試験を適正に行う視点から工業所有権審議会が相当と認めた得点以上であること
- 合格基準点の改正
平成28年(2016)年度より、科目別合格基準が導入されています(各科目の40%程度の得点が基準)。これにより、従来のように得意科目を磨き上げる学習計画ではなく、出題される全ての科目において十分な対策を漏れなく行うことが必須となりました。
1. 2次試験 論文式筆記試験(知識の応用能力を問われる試験)
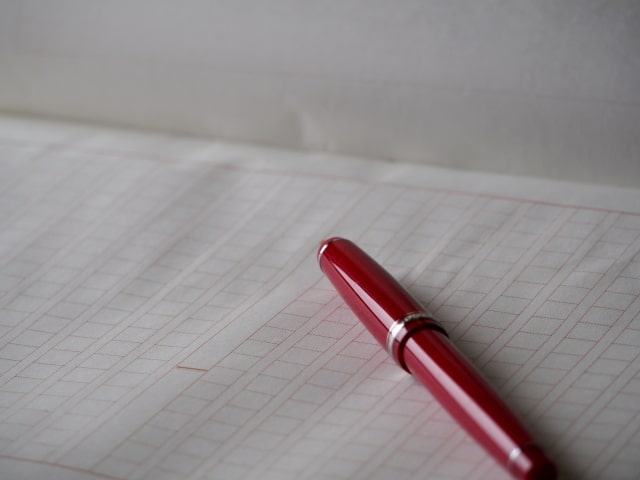
論文式筆記試験は、弁理士活動を行うにあたって必須となる条文の解釈及び理解力、判断力、論理的展開力、文章表現力等の総合的思考力を問う試験です。必須科目、選択科目の2段階で実施されます。両方の科目の試験を通過することで論文式筆記試験合格となります。
- 受験資格
短答式筆記試験 合格者、短答式筆記試験 免除者 - 試験日
【必須科目】6月下旬~7月上旬
【選択科目】7月下旬 - 試験地
東京、大阪 - 合格発表
9月下旬 - 免除対象者
免除制度の詳細につきましては、特許庁ホームページをご覧ください。 - 試験概要【必須科目】
- 試験形式 論文式(試験の際、弁理士試験用法文の貸与あり。)
- 試験科目 工業所有権(特許・実用新案、意匠、商標)に関する法令の3科目
- 試験時間
- 特許・実用新案:2時間
- 意匠:1時間半
- 商標:1時間半
- 合格基準 標準偏差による調整後の各科目の得点の平均(配点比率を勘案して計算)が、54点を基準として口述試験を適正に行う視点から工業所有権審議会が相当と認めた得点以上であること。
ただし、47点未満の得点科目が一つもないこと。
- 試験概要【選択科目】
- 試験形式 論文式(試験の際、法律科目受験者には弁理士試験選択科目用法文貸与あり。)
- 試験科目 6科目の中から1科目を選択
※選択科目は「選択問題」まで願書提出時に選択
※改正注2 平成28(2016)年度より、選択問題は15に集約されています。- 理工Ⅰ(機械・応用力学)/材料力学・流体力学・熱力学・土質工学
- 理工Ⅱ(数学・物理)/基礎物理学・電磁気学・回路理論
- 理工Ⅲ(化学)/物理化学・有機化学・無機化学
- 理工Ⅳ(生物)/生物学一般・生物化学
- 理工Ⅴ(情報)/情報理論・計算機工学
- 法律(弁理士の業務関する法律)/民法(総則、物権、債権から出題)
- 試験時間 1時間半
- 合格基準 選択科目の得点(素点)が満点の60%以上であること
3. 3次試験 口述試験(口頭での応答能力を問われる試験)

口述試験は、論文式筆記試験で確認された総合的思考力等に基づいた、口述による説明力を問う試験です。
- 受験資格
論文式筆記試験最終合格者 - 試験日
10月中旬~下旬 - 試験地
東京 - 合格発表
10月下旬~11月上旬 - 免除対象者
特許庁において審判または審査の事務に5年以上従事した方 - 試験概要
- 試験形式 面接方式
※受験者が各科目の試験室を順次移動する方法により実施。 - 試験科目 工業所有権(特許・実用新案、意匠、商標)に関する法令
- 試験時間 3科目それぞれについて、10分程度
- 合格基準 採用基準をA、B、Cのゾーン方式とし、Cの評価の科目が2科目以上ないこと
- 試験形式 面接方式
- 免除制度(2年間有効)
弁理士試験には、受験免除制度があります。公的資格等による免除もありますが、短答式筆記試験、論文式筆記試験必須科目は、合格により、翌年及び翌々年の受験が免除となります。
つまり、一度短答式試験に合格すると翌年の試験以降計2回、短答式試験を受験しなくても論文式試験に挑戦できるということです。また、一度論文式筆記試験必須科目(短答式試験に合格することが受験資格)に合格すると翌年の試験以降計2回、論文式筆記試験必須科目を受験しなくてもよいということです。
この免除制度を上手に活用することで、効率的かつ戦略的に最終合格を目指すことができます!
| 【例】 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 短答本試験 | 合格 | 免除 | 免除 |
| 論文本試験【必須科目】 | 不合格 | 合格 | 免除 |
| 論文本試験【選択科目】 | 合格 | 免除 | 免除 |
| 口述試験 | 不合格 | 合格=最終合格! |
弁理士試験科目
- 特許・実用新案法
特許法及び実用新案法は、発明や物の形状等の考案の保護を図る一方、その発明等を公開し技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようという法律です。 - 意匠法
意匠法は、物品のより美しい外観、使ってより使い心地のよい外観を探求し、美感の面から創作を保護しようとする法律です。 - 商標法
商標法は、商標に対しそれが付された商品等の出所を表示する機能等を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようという法律です。 - 工業所有権に関する条約
パリ条約、特許協力条約(PCT)、TRIPs協定、マドリッド協定の議定書、ハーグ協定のジュネーブ改定協定等、産業財産権に関連する国際条約です。 - 著作権法及び不正競争防止法
著作権法は文芸、学術、美術、音楽等精神的作品を保護するものであり、不正競争防止法は商品形態の模倣行為等やノウハウ等の盗用を不正競争行為として規制するものです。
弁理士の勉強方法
弁理士試験を勉強する方法は大きく3つあります。
- 通学の学校に行って勉強する。
- 通信の学校で勉強する。
- 独学で勉強する。
どの方法がより効率的に勉強できるか考えてみましょう。

弁理士の試験は独学で合格できる?
弁理士の試験は、専門知識を要する難関の資格試験の一つとして知られています。多くの人々は専門の学校や予備校を利用してこの試験に挑むことが一般的ですが、独学での合格者も少なくありません。では、実際に独学で弁理士の試験に合格することは可能なのでしょうか。
弁理士を独学するメリット
弁理士を独学するメリットとしては以下が挙げられます。
- コストの節約
独学で学習することで、専門学校や塾などの受講料を節約できます。教材費用のみで資格を取得することが可能です。 - 自分のペースで学習
独学の最大のメリットは、自分のペースで進められる点です。忙しい時期は少しペースを落とし、時間が取れる時期は集中的に学習することができます。 - 学習環境の選択
自宅、図書館、カフェなど、自分が集中しやすい環境で学習が進められます。 - 自分に合う学習方法を選べる
独学では、自分の得意な学習方法やリズムを選べます。動画、書籍、模擬試験、インターネットの情報源など、様々な方法で学習資料を組み合わせることができます。 - 自分自身の成長
独学は、自己管理能力や調査能力、持続力など、様々なスキルを養成する良い機会です。
弁理士を独学するデメリット
しかし、独学のデメリットもあります。例としては以下が挙げられます。
- モチベーションの維持が難しい
一人で学習を進めるため、挫折しやすくなる可能性があります。同じ目標を持つ仲間や講師からのフィードバックがないため、自分を奮い立たせるのが難しい場合があります。 - 情報の過不足
独学の場合、何が必要で何が不要な情報かを判断するのが難しい場合があります。また、古い情報や誤解を招く情報に触れるリスクも高まります。 - 最新情報のキャッチアップ
専門学校や塾は最新の試験傾向や変更情報を迅速にキャッチアップして提供してくれますが、独学の場合は自分でその情報を探さなくてはなりません。 - 学習の方向性の迷い
専門の指導者やカリキュラムがないため、どの範囲や順番で学習を進めればよいか迷うことがあります。 - 実践的なスキルの不足
独学では理論的な知識は得られますが、実際の業務や実技に関するスキルは独学だけでは習得が難しい場合があります。 - 質問や疑問の解消が遅れる
講師や先輩受験生にすぐ質問することができないため、疑問点がそのまま放置されることがあります。
弁理士試験を独学で合格するためのポイント
弁理士試験を独自の勉強方法で合格している人は、どのような勉強方法をしているのでしょうか。
独学で勉強したい人におすすめなのは、大手専門学校をうまく利用することです。
独学を考えている人の大部分は通学時間と受講費用に問題があると思われます。
それらを解決できるのが、通信教育講座も行っている「LEC」と「資格の学校TAC 」です。最新の試験範囲が網羅できているばかりでなく、試験勉強における重要度による強弱や勉強のペース配分などがわかります。
弁理士は年収いくら稼げる?年齢別に紹介
弁理士という職業は、特許、商標、デザイン権などの知的財産に関する法的な手続きを専門とする資格を持った専門家です。この記事では、弁理士の平均年収と、年齢別の年収について詳しく解説していきます。
弁理士の平均年収
弁理士の仕事は非常に専門的なスキルと知識が求められるため、それに見合った報酬が支払われることが一般的です。弁理士の平均年収は945万円とされています。この数字は、企業での勤務や独立して開業する場合、経験年数や実績、働く地域、さらには担当する業務の内容によって大きく変動することもあります。
年齢別の弁理士の年収
年齢とともにスキルや経験が積み重なるため、弁理士の年収も年齢によって変動が見られます。以下に、年齢別の年収の一般的な範囲を示します。
- 20代の年収:300万~550万円
新卒やキャリアが浅い20代の弁理士は、多くの場合、基本的な業務からスタートするため、年収は比較的低めです。 - 30代の年収:850万~950万円
30代になると、多くの弁理士が一定の経験とスキルを持っています。それが反映され、年収も高くなります。 - 40代の年収:1,000万~1,050万円
40代はキャリアが頂点に達する時期とも言えます。専門性が高く、多くの案件を引き受けることが可能です。 - 50代の年収:900万~1,200万円
50代になると、経験と知識は豊富ですが、新たな技術や法改正に対応する必要があります。それでも、高い年収を維持する弁理士も少なくありません。
年齢が上がるにつれて、弁理士の年収は一般的に上昇傾向にありますが、それは継続的な学習と努力が必要な職業であるとも言えます。弁理士を目指す方、すでに弁理士として働いている方にとって、この情報が参考になれば幸いです。
弁理士の資格は就職に有利?資格の特徴とメリット・デメリットを紹介
弁理士(特許業務従事者)という資格は、特許や商標、意匠などの知的財産権に関する業務を専門的に行う人々のことを指します。この資格を持っていると、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。特に、就職や転職において弁理士の資格は有利なのでしょうか。ここではそれについて解説します。
弁理士が就職や転職に有利な理由
- 専門知識が求められる場面が多い
弁理士の資格を持つことで、特許申請や知的財産権に関する専門的な業務が行えます。このような業務は一般的なビジネスマンには難しいため、専門知識を求められることが多いです。 - 幅広い業界での需要
製薬業界からIT、エネルギー業界まで、多くの分野で知的財産が重要視されています。そのため、弁理士は多様な業界で需要があり、転職市場でも高い柔軟性を持っています。 - 立場が強い
弁理士は企業において、特許戦略を立てる立場になることが多く、その意見は重要視されます。このような責任のあるポジションにつくことが多いため、キャリアパスも広がります。
弁理士を持つことによる就職のメリット・デメリット
メリット
- 専門職としての高収入
弁理士は専門性が高いため、その報酬も一般的なビジネスマンよりも高い傾向があります。 - キャリアの多様性
弁理士の資格を持っていると、特許事務所はもちろん、企業の内部ポジションや独立して事務所を開くなど、多様なキャリアパスが開かれます。 - 国際的な活躍の場もある
弁理士の資格は、海外での業務にも役立つ場合があります。特に、多国籍企業ではその専門性が高く評価されることが多いです。
デメリット
- 勉強の負担
弁理士の試験は非常に難易度が高く、合格するまでには多くの時間と労力が必要です。 - 専門性が高すぎる
あまりにも専門性が高いため、そのスキルが他の業務に活用しにくい場合があります。 - ストレスと責任の大きさ
弁理士は企業の特許戦略に大きく関わるため、その責任も相応に大きいです。その結果、ストレスがかかることも少なくありません。
以上のように、弁理士の資格を持つことには様々なメリットとデメリットがありますが、専門性が高く評価される職種であるため、多くの場合、就職や転職において有利な条件をつけられることが多いです。弁理士の道に進みたい方は、実績のある学校や予備校にて学ばれることをおすすめします。
弁理士の合格率は?
弁理士試験の合格率
弁理士試験の合格率は直近5年間で6.1%~9.7%です。国家資格試験の中でも難易度が高い資格に位置付けられています。
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| 令和4年度 | 6.1% |
| 令和3年度 | 6.1% |
| 令和2年度 | 9.7% |
| 令和元年度 | 8.1% |
| 平成30年度 | 7.2% |
弁理士試験の年代別の合格率
令和4年度(2022年度)における弁理士試験の年代別の合格率は以下の通りです。
| 年代 | 合格率 |
|---|---|
| 20歳代 | 34.2% |
| 30歳代 | 36.3% |
| 40歳代 | 22.3% |
| 50歳代 | 6.7% |
| 60歳代 | 0.5% |
弁理士試験の職業別の合格率
令和4年度(2022年度)における弁理士試験の職業別の合格率は以下の通りです。
| 職業 | 合格率 |
|---|---|
| 会社員 | 45.6% |
| 特許事務所 | 33.2% |
| 無職 | 6.2% |
| 公務員 | 4.7% |
| 学生 | 3.1% |
| 法律事務所 | 2.1% |
| 自営業 | 1.0% |
| 教員 | 0.0% |
| その他 | 4.1% |
弁理士試験の男女別の合格率
令和4年度(2022年度)における弁理士試験の男女別の合格率は以下の通りです。
| 性別 | 合格率 |
|---|---|
| 男性 | 68.9% |
| 女性 | 31.1% |
弁理士試験に合格するまでの勉強時間は?
弁理士試験に合格するための標準勉強時間は3,000時間が目安とされています。参考までにいくつかの資格の勉強時間について下の表で比較しました。
| 資格名 | 勉強時間 |
|---|---|
| 公認会計士 | 3,500時間 |
| 司法書士 | 3,000時間 |
| 社会保険労務士 | 800時間~1000時間 |
| 行政書士 | 600時間~700時間 |
| 弁理士 | 3,000時間 |
公認会計士や司法書士とほぼ同等です。毎日4時間の勉強をするとしても約2年間は必要になりますし、3,000時間の学習時間を達成するには効率的な学習をしていく必要があります。効率的な学習をしていくのであれば学校や予備校にて学ばれることをおすすめします。
弁理士は役に立たない?無意味な資格と言われる理由を解説
弁理士という職業は、知的財産権の専門家として評価されていますが、一方で「役に立たない、無意味な資格」とも言われています。以下でその理由をいくつか解説します。
弁理士が役に立たないと言われる理由
弁理士という資格について、ネット上で検索すると以下のような声も一部あります。
「弁理士は役に立たない」
「弁理士はやめとけ」
「弁理士はオワコン」
このような声の理由として、以下が考えられます。
- 国内市場の飽和と競争激化
弁理士の数が増加しており、特に都市部での競争が激化しています。加えて、弁理士の仕事量は日本国内の特許出願件数の減少によっても影響を受けているようです。 - 高い責任と負担
弁理士は基本的に単独で業務を行うため、責任が非常に重く、企業からの要求も増加しています。これがストレスとなり、長期的なキャリアに疑問を投げかける原因となっています。 - 専門性とスキルの投資
弁理士は高い専門性と責任が求められる仕事です。企業からの要求も増えて多様化しており、一人前になるまでに時間と努力が必要です。
これらのポイントが、弁理士が一部で「無意味な資格」「役に立たない」と評価される理由のようです。
弁理士が無意味な資格ではないと言い切れる理由
弁理士が無意味な資格ではない理由を以下にいくつかの紹介します。
- 国外の特許ニーズ増加に対応する専門職
国際特許出願数が増加する中で、専門的な知識と技術が必要とされています。 - 高い報酬とキャリアの多様性
一般的な会社員と比較して報酬が高い場合が多く、フリーランスやリモートワークといった柔軟な働き方も可能です。そのため、個々のライフスタイルやキャリアプランに柔軟に対応できます。 - AIによる代替えが困難な仕事
AIの進化が多くの職種に影響を与える中、弁理士は法的なニュアンスや戦略的な判断が必要なため、AIによる置き換えが困難だといわれます。そのため、将来的にも持続的な需要が見込まれます。
弁理士に合格すると人生が変わる?弁理士のメリット5選
弁理士としてのキャリアを積むことで、多くのメリットが生まれます。その主な点をいくつか紹介しましょう。
- 多業界での仕事機会
弁理士は特許や知的財産に関わる多くの業界で働くことができます。それによって、多様なビジネスパートナーとの繋がりが広がります。 - 国際的なビジネス
特許問題は国際的な規模で扱われることが多いため、海外とのビジネスもスムーズに行えます。これにより、グローバルな人脈と知識が得られます。 - 働き方の自由度
弁理士の専門性が高いため、テレワークやフレキシブルな働き方が選べます。これは、プライベートとのバランスを取りやすくする大きなメリットです。 - 年収の高さ
弁理士はその専門性から、高い年収が期待できます。安定した経済基盤を築くことが可能です。 - キャリアの多様性
弁理士として働く場合、企業に所属する形態からフリーランス、独立まで、多様な働き方が選べます。これによって、キャリアの選択肢も広がります。
これらのメリットを通じて、弁理士という職業は多くの可能性と選択肢をもたらします。それが人生に与える影響は計り知れないものと言えるでしょう。
【公式サイト】資料請求
パンフレット請求・受講相談・体験受講・割引申込一覧
下記に 弁理士の学校の「公式サイト」一覧を「オンラインWeb通信・独学向きの学校」「通学向きの学校」ごとにまとめています。
当サイトの各リンクページはすべて「公式サイト」のため、パンフレット請求をはじめ、下記のようなことができます。

・パンフレット取寄せ(無料請求フォームあり)
・受講相談(オンライン、メール、対面相談等)
・体験受講(Web体験講義、DVD体験受講等)
・割引申込等(期間限定割引、クーポン表示、継続割引等)★★★
期間限定割引案内、クーポン等が表示されることがありますので、必ず「公式サイト」から申し込みましょう!
各リンク先が「公式サイト」になります。各TOPページでご確認ください。
パンフレット請求等一覧
オンラインWeb通信教育・独学向きの学校のパンフレット請求等
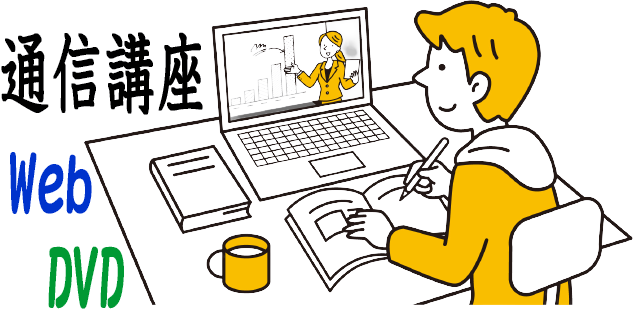
通学・通信向きの学校のパンフレット請求等
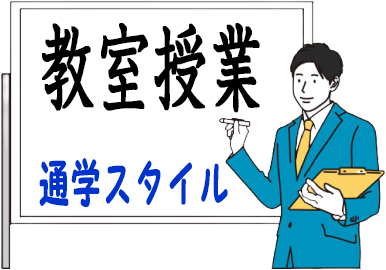
弁理士とは

産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決をスムーズに行うことができる、唯一の国家資格です。弁理士は、特許法等を代表とする「知的財産法」を取り扱う法律家です。
「知的財産法」の対象は、知的活動などから生み出されるアイデア等であり、その扱いは非常に難しいものです。そのため取り扱いには高度な専門性が求められます。
その高度な専門性を取得した弁理士だからこそ、アイデア・デザイン・創作物などの知的創作についての特許権・意匠権・商標権などを工業所有権の権利取得をするための特許庁に出願代理することができるのです。また、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の取得や紛争解決は、高度な技術的・法律的・実務的知識を必要とします。
「知的財産権」とは、人間の知的活動によって生み出されたアイディアや創作物などには、財産的価値を持つものがあり、それらを総称して「知的財産」と呼びます。知的財産には、発明・考案・著作物・意匠・商標・商号などがあり、その知的財産について、その創作者に一定期間法律で保護を与えているのが、知的財産権です。知的財産権のうち、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つを「産業財産権」といいます。
弁理士の業務

弁理士の仕事は大きく分けると3つ。今後さらに活躍が期待される資格です。
現在、「産業財産権の取得(独占業務)」が大きなウエイトを占めていますが、企業の環境の変化により、将来は「コンサルティング業務」や「紛争解決業務」の需要が増えてくると言われています。
企業の知的財産に関する戦略を立案し、助言するコンサルタント能力を持った弁理士が求めらます。
クライアントの説明をきいて、ポイントはどこになるのかを理解し、それを文章にまとめるためには、聞き出す能力、助言する能力が必要です。クライアントによっては、膨大な資料を用意してくる人、逆に全く資料がなく口頭で説明するだけの人、人によってそれぞれです。
そういった場合でも、関連書籍を何冊も読み、クライアントの期待に沿った明細書が作成する努力も必要です。
産業財産権の取得(独占業務)

特許権・実用新案権・意匠権・商標権などを取得したい人に代理して特許事務を行う仕事です。弁理士の独占業務であり、主な仕事となります。
- 権利の取得
特許権・実用新案権・意匠権・商標権等の権利を取得するための出願手続の代理等の業務をいいます。高度な技術的・法律的知識が要求されるため、弁理士しか行うことのできない独占業務とされています。- 特許
依頼者の依頼内容をくみ取り、特許出願にかかる作業をサポートします。ほとんどの発明者が資料を用意せずに、口頭で説明する場合が多いです。そのため弁理士が発明のポイントをくみ取り、それを資料にとめ、特許がとれるかどうか判断します。その後、特許に必要な出願書類を提出します。特許を取得するには様々な手続きが必要です。 - 実用新案
アイディアについて依頼者から相談を受け、それが実用新案登録の対象になるか判断します。実用新案として出願できる場合は、出願書類を作成し出願手続きをします。アイディアが良くても出願書類に不備があると、きちんと実用新案をとることができません。弁理士は技術的な知識と法律的な知識が必要です。 - 意匠
依頼人から意匠登録の依頼を受けた際には、そのデザインの特長や製品の機能・用途等をしっかりと聞き取り、意匠内容に係る物品の特定や必要な図面の検討を依頼者とともに行います。出願する場合には、出願書類を作成し、出願手続きを行います。出願後特許庁から通知が届いたら、依頼者の登録料の納付や意見書の提出などを行い権利化します。登録後は、意匠登録料(維持年金)の納付期限等の管理も行います。 - 商標
依頼者から商標登録出願の依頼を受けた場合には、対象となる商品やサービス、商標の対象等を検討し、出願出来るかどうか事前調査を行います。出願する場合は出願書類を作成し、出願手続きを行います。出願後、特許庁から通知が来たら必要に応じて登録料の納付や意見書の提出などを行います。登録後は更新期限の確認も必要です。
- 特許
- 鑑定・判定・技術評価書
弁理士は、代理人として発明や考案や意匠の範囲がどこまで及ぶか、商標が類似しているか否かについて鑑定、特許庁の見解を求めるため、クライアントの代理人として判定請求を行います。さらに、実用新案権は実質的に無審査で取得できる権利ですので、権利の有効性を確認するために、クライアントの代理人として特許庁に対して技術評価請求、得られた技術評価書の内容について鑑定を行います。 - 外国における産業財産権の取得及び対応
弁理士は、クライアントが外国で発明や商標について権利を取得したいとき、複雑な手続きを代行します。そのために、弁理士は外国の提携弁理士と手紙やファクシミリなどで法律改正などの情報交換をしたり、直接会って意思の疎通を図るなど、常に国際的な交流を続けています。
産業財産権の紛争解決

工業所有権、回路配置利用権、特定不正競争などの訴訟については、従来訴訟代理人となれるのは弁護士のみであり、弁理士の役割は補佐人として陳述・尋問するに留まっていました。
しかし現在では弁理士に侵害訴訟の訴訟代理権が与えられるようになり、産業財産権の紛争解決で弁理士が大きな役割を果たせるようになっています。
- 訴訟
クライアントが審判の審決に不服なとき、代理人としてその審決の取り消しを求める訴訟を裁判所に起こします。またクライアントが権利侵害の訴訟を起こしたり起こされたとき、弁理士は一定要件のもとで弁護士と共同であなたの訴訟代理人として、又はあなたや代理人の補佐人として訴訟を有利に展開させます。 - 裁判外紛争解決手続(ADR)
クライアントに代わって裁判外で、特許権、実用新案権、意匠権もしくは商標権又はJPドメイン名について、日本知的財産仲裁センターが行う裁判外紛争解決(ADR)手続や、回路配置利用権または特定不正競争に関する裁判外紛争解決の手続代理をします。 - 輸出入差止
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などを侵害する物品について、関税法に規定された認定手続並びに認定手続を執るべきことの申立及び申立に関する手続において、権利者の代理のみならず輸入者及び輸出者の代理を行います。
取引関連業務・コンサルティング業務

人間の知的創作であるにもかかわらず、無形の財産であるがゆえに長らく国民の認識が低かった知的財産ですが、国を挙げての知的財産戦略の強化促進により知的所有権の概念は社会に浸透しており、それに伴って弁理士のニーズは高まりました。しかし弁理士同士の競争激化や環境の変化により、他の弁理士との差別化が必要となっています。
そこで、独占業務のみならず包括的なサポートを提供する弁理士が増えています。
- 取引関連業務
知的財産権の売買契約やライセンス交渉の代理、媒介業務や、それらの相談に応ずる業務などがあります。評価業務と合わせ、取引業務まで総合的にサポートできる弁理士が期待されています。 - 契約の締結等
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約などの締結をクライアントに代わって行ったり、媒介や相談にも応じます。 - 著作権管理業務
産業財産権以外の知的財産権、例えば著作権(絵画、音楽、コンピュータプログラム)や半導体集積回路配置などは産業財産権に隣接する法域で認められるものであるため、これらに関しても適切なアドバイスを行います。
講演・執筆活動
知的財産専門職大学、法科大学、その他の大学・大学院でも知的財産に関する講義が設けられているため、大学での講義をしたり、企業その他での講演、執筆活動を行います。
特許出願から特許されるまでの流れ
1.先行技術検査を行う
出願前に既に同じような技術が公開されていないか調査を行います。
先に同じような特許が取得されていれば、特許を出願することができなくなります。また、特許権が設定されている技術を無断で使うと特許権の侵害となる可能性もあります。特許出願が無駄にならないよう、念入りな調査を行うことが重要です。
2.特許出願書類の作成・提出
法令で定められた所定の出願書類を特許庁に出願します。提出には、通常、次の書類を提出します。
- 特許願(願書):出願人・発明者の情報などを記載
- 明細書:発明についての技術的説明
- 特許請求の範囲:権利を取りたい発明の範囲
- 図面:説明するための図案や写真
- 要約書:発明の概要
出願には、書類で提出する方法とインターネットで提出する方法があります。
3.方式審査
出願書類が法令で定められた所定の方式的要件を満たすかどうかのチェックがなされます。これはあくまでも方式のチェックであり、実体に関する審査ではありません。不備がある場合は、補正指令が発せられるか又は出願却下となります。
4.出願公開
出願日から1年6ヵ月経過後、出願書類が公開されます。出願から1年6ヵ月経過前であっても、出願人の申請により出願公開を行うことがあります(早期出願公開制度)。
5.出願審査請求
出願審査請求がなされた出願について、実体審査が行われます。出願審査請求には審査請求料が必要です。出願審査請求は出願日から3年以内であればいつでもすることができます。
6.早期審査申請
一定の要件のもと、審査を早期に行ってもらうことができます。要件を満たす説明を記載した事情説明書の提出が必要となります。またさらに他の要件を満たせば、早期審査よりさらに早く審査を行う「スーパー早期審査」を申請することもできます。
7.情報提供
特許出願がなされた後は、特許付与後であるかにかかわらず、誰でももいつでも特許性を否定する情報を提供することができます。これは匿名ですることも可能です。
8.実体審査
法律で規定された拒絶理由がないかどうかを特許庁の審査官が審査します。拒絶理由があると認められた場合は、「拒絶理由通知書」が通知されます。出願人は拒絶理由を解消するために「意見書」「手続き補正書」を提出します。拒絶理由がないと認められれば「特許査定」が通知されます。拒絶理由があると最終的に判断されると「拒絶査定」が通知されます。
9.拒絶査定不服審査
「拒絶査定」に不服がある場合は「拒絶査定不服審判」を請求することができます。まずは、審判請求時の補正が適法なものであったか、の審査が行われます。特許庁の審判部で審判官により拒絶査定を維持すべきか否かが審理されます。ここで維持べきとなれば拒絶すべき旨の審決がなされ、拒絶理由は覆されるべきとなれば特許すべき旨の審決がされ、特許料を納付すれば特許となります。
弁理士の仕事の今後について
2002年に知的財産企保運法が公布されて以来、知的財産権に関する関心は高まっています。知的財産権の保護は、ビジネスを行っていくうえで重要な位置を占めています。インターネットの普及、IT革命の到来により、AIやIoT(Internet of Things)関連の特許出願も増えていくと予想されます。さらには、日本国内のみならず、特許出願もグローバル化しており、弁理士として活躍の場は増えていきそうです。商標登録については、以前は、文字、記号、図形からなる平面商標や立体商標であり、かつ、静止した商標に限られていましたが、2015年4月からは、音、動き、ホログラム、一の商標、色彩のみからなる商標を出願できるようになっています。知的所有権を戦略的に活用することが、企業にとって大事なビジネス要素にもなってきており、弁理士のニーズは高まっています。
さらには、弁理士の侵害訴訟の代理権付与、弁理士報酬に対する料金表の廃止、特許業務法人の設立が可能になりました。
昔に比べ、弁理士の登録者数は、増加しています。それに伴い、競争の激化が起こっています。その競争に勝ち抜くためには、弁理士試験に合格した後も、知識の向上など、弁理士としての資質向上が求められています。その為、以前はなかった義務研修が設置されています。
弁理士は、ライブやオンラインで講義を受け、一定単位の取得が必要となりました。
資格を輝かせる弁理士の世界
弁理士という資格は、自分に合った様々な働き方を選択できます。
弁理士は「独立開業(特許事務所経営)」、「特許事務所勤務」「メーカーの特許部、知的財産部勤務」など、自分のプランに合った様々な働き方を選択することができます。
特許・法律事務所経営・勤務
特許事務所等に勤務する弁理士は、自己の専門知識を活用しながら、得意分野を広げます。出願申請を通過するにはどのような申請内容にするか、企業にアドバイスを行います。
「開業弁理士」として独立する場合は、通常の知財業務だけでなくさらに事務所の経営面まで広く携わる必要がでてきます。多くの専門資格でもいえることですが、試験合格後いきなり開業して働く方は少数派で、まずは特許事務所で知識と実務を身につけてから独立する人が多いです。
最近は、クライアントと顧問契約を結び、毎月一定額の顧問料をもらう形態も増えてきています。顧問契約を獲得できた時は開業弁理士ならではのやりがいと喜びを味わうことができるでしょう。
企業内弁理士
知的財産は企業活動においても重要な位置を占めるため、知的財産部などの専門的部署を設ける企業もあります。企業内弁理士は、そういった企業の知的財産権専門の部署(知財部・法務部)等に所属し、業務内容は出願から訴訟まで広く包括的に関与できます。
企業内弁理士が勤務している会社の一例:
㈱日立製作所、Panasonic㈱、㈱Nikon、京セラ㈱、㈱野村総合研究所、TDK㈱、東レ㈱、㈱リコー、テルモ㈱、㈱東芝、味の素㈱、三菱重工業㈱、日本IBM㈱、武田薬品工業㈱、㈱ブリヂストン、富士通㈱、キヤノン㈱、出光興産㈱、三菱電機㈱、ソニー㈱、協和発酵キリン㈱、オリンパス㈱、富士ゼロックス㈱、アステラス製薬㈱、第一三共㈱、三菱マテリアル㈱、カシオ計算機㈱、㈱トムソン技術研究所、日本技術貿易㈱、大正製薬㈱、帝人㈱、メディキット㈱、富士電機㈱、日本電気㈱、花王㈱、本田技研㈱
日本においては先願主義を採用しているため、過去の内容に類似しないよう独自性を主張し、権利化に結びつけることが求められます。企業内弁理士であれば、経営戦略に関わる総合的な経験を積むことができます。
大学・研究機関
弁理士は、大学や研究機関でされた発明の特許権を取得・保護し、さらにこの発明を企業にライセンス許諾して社会に役立てるなど、研究の成果を適切に活用し、社会に普及・還元します。
これは、知的財産の専門家として、更に、産学連携や研究スタッフの一員としての活躍が期待されている証拠で、大学・研究機関と社会の橋渡しの役割を果たす重要な業務です。
知的財産コンサルティング
「知的財産コンサルティング」として、知財を活かしながら、経営に関する知識、センスを向上させ、クライアントへの経営や収益改善アドバイス、さらに知財を活かした新規事業創出に貢献など、弁理士業務のサービスの付加価値を高める業務を行います。
中小企業診断士との連携
わが国の経済基盤は、ものづくり中小企業等が支えており、中小企業、ベンチャーの役割に大きな期待が寄せられています。そうした中、中小企業診断士と弁理士が相互の業務内容を理解し、情報交換を行い、弁理士業務として、中小企業・ベンチャー支援に取組み、協業できるビジネススタイルを開拓することも期待されています。
国際派
「知財」の世界は、日本国内だけにとどまりません。そのため、国際規模で知的財産を保護する必要があり、クライアントの競争力強化のために、国内だけでなく海外での権利取得も視野に入れて戦略を立てられる弁理士が必要とされてきています。
「国際特許事務所」とは特許を海外に出願する、または海外から日本に特許を出願する際の国際業務を行っている事務所を指しますが、「特許事務所」の名称があるところでもこのような国際業務を行っているのが通常です。
特許の権利というのは世界各国でそれぞれ別々にとらなければ保護されません。とはいえ世界中のすべての国で特許を取得するのはほぼ不可能ですので、出願人はビジネスの展開先の国を選んでこれらの国々でも特許出願する手続きをします。
しかし、外国に出願するには当地の特許弁護士に手続きをとってもらう必要があります。このとき英語力が必要とされます。そのため特許事務所では英語の堪能なスタッフの需要が生まれ、「外国出願担当者」の求人が行われています。
従って、国際化の進んでいる今「特許事務所」という看板を掲げている事務所でも、国内出願のみならず外国出願を依頼できると考えてよいでしょう。
弁理士の学校の評判・口コミ
弁理士の学校に通った方の評判・口コミを一部を抜粋してご紹介します。
LECの口コミ
LEC(東京リーガルマインド)に通った人の評判・口コミです。
・資格がくれたのは大きな可能性!
私が受講したベーシックコースでは、まず入門講座で体系的に学び、短答基礎力完成講座で細かい知識を得ます。
一度入門講座でざっと体系的に学ぶことによって、短答基礎力完成講座で自分が今どこを勉強しているのかわからなくなることを防げるのが良いと感じました、宮口先生の講義では、蛍光ペンでテキストに入ろを付けていきます、勉強をしていると暗記をしなくてはいけない部分が少なからずありますが、色分けをすることでぶんしょうにメリハリがつき覚えやすくなります。私自身、この勉強方法でとてもたすけられました。
弁理士試験合格までの道のりは険しく、何度やめたいと思ったかわかりません、しかし、辛い思いをしても取得する価値のある資格だと思います。私自身、資格試験で人生が変わったと感じています。
・「短答アドヴァンステキスト」×その生みの親による優位積むにのコースで難関突破!
仕様教材の一つである「短答アドヴァンステキスト」は、短答試験突破に必要な事項がすべて含まれており、複数のテキスト・レジュメを参照せずとも短答対策がこれ一冊で完結する素晴らしい教材でした。
過去問や短答実践答練で理解不足が露呈した事項は、随時短答アドヴァンステキストに「一元化」することにより、自分の知識の穴・弱点を効率的に復習できました。短答アドヴァンステキスト&その生みの親である佐藤先生の講義により、近年難化している短答試験を突破することができました。
・初年度は短答試験に的を絞って一発合格!
秋からの開始だったため、論文対策まで欲張りたい気持ちを抑え短答速習コースを選択しました、初学者の私には難しく感じることもありましたが、佐藤先生が示してくださる勉強の進め方に従う事で、無事、短答試験を突破することが出来ました。
振り返ると自分には論文試験の対策まで手を回す時間も余裕もなかったので、初年度は短答試験に的を絞るという計画は、決して遠回りな方法ではなかったと思います。短答特化型の講座でありながら、論文試験にも通用する知識までもインプット出来ました。最終合格を目指す上での基礎を固めていただいた佐藤先生には本当に感謝しています。
・入門講座を徹底復習!
初回受験合格者の合格率が特に高いという実績を見た瞬間、LECで勉強することを決意しました。
1年合格を志す私にとって、その数字は他の予備校等を検討しないのに充分なものでした。本質的な部分からきっちり学習したかったので、パンフレットをみてピンときた佐藤戦士の入門講座を選択しました。
佐藤先生の講義は知的財産権法の面白さを味わいつつ、弁理士試験に必要な知識や考え方を余すことなく得ることが出来るものでした。私は特に入門講座を何度も何度も聴きなおしました。コースが進んで法律相互間の関係性が分かり、比較ができる様になった上で聴くと最初の頃はそんなものかな、と思って流していた話に深く納得することができ、感動すら覚えるほどです。
テキスト類は冊数が多く暑さもなかなかのものですが、それぞれ必要な丈夫がまとめられているので重宝しました。やるからには一発合格!と掲げていどみ、これを果たせた達成感は大きいです。短い期間ではありましたがLECに通い勉強したことは大きな経験になりました。
・覚悟と前進
LECを選んだのは、大手の予備校で実績があり、LECのスケジュールで勉強すれば、自分であれこれ考える無駄な時間を使わなくて済むと考えたためでした。入門講座の初回の講義で、「復習で優先すべきは講義の音声データを2回聞くこと」と具体的な指示があったため、復習方法には迷うことなく、その指示に従いました。また、勉強時期に応じた勉強時間の目安についてもお話があり、合格までのイメージを掴む事ができ、「納富先生についていけば1年で合格できる!と確信したことを覚えています。
納富先生は重要な部分は講義の中で繰り返し強調しておっしゃるので、覚えようと思わずとも耳に残り、自然と身についていたった感覚があります。このように、納富先生は講義時間外の過ごし方のお話もしてくださるので、納富先生のご指導なくしては私の合格はなかったです。
通学の弁理士の学校・予備校(専門学校)の開講場所
社会人や学生におすすめの通学の学校の校舎一覧はこちらです。
通学の弁理士の学校・予備校(専門学校)の開講場所です。
※校舎が変更になる可能性がございますので、パンフレット請求でご確認ください。
「LEC(東京リーガルマインド)」の教室講座の開講場所
北海道・東北地区
<北海道>
・札幌本校
・北見駅前校【提携校】
<青森>
八戸中央校【提携校】
・弘前校【提携校】
<秋田>
・秋田校【提携校】
<宮城>
・仙台本校
関東地区
<茨城>
・水戸見川校【提携校】
<埼玉>
・大宮本校
・熊谷筑波校【提携校】
・所沢校【提携校】
<千葉>
・千葉本校
<東京>
・水道橋本校
・池袋本校
・新宿エルタワー本校
・早稲田本校
・渋谷駅前本校
・立川本校
・中野本校
・町田本校
・新橋本校
・東京駅八重洲口校【提携校】
・日本橋校【提携校】
・新宿三丁目駅前校【提携校】
<神奈川>
・横浜本校
甲信越・北陸地区
<新潟>
・新潟校【提携校】
<富山>
・富山本校
<福井>
・福井南校【提携校】
<石川>
・金沢校【提携校】
中部地区
<静岡>
・静岡本校
・沼津校【提携校】
・浜松駅西校【提携校】
<愛知>
・名古屋駅前本校
関西地区
<三重>
・名張校【提携校】
<滋賀>
・滋賀草津駅前校【提携校】
<京都>
・京都駅前本校
・EYE京都本校
<大阪>
・梅田駅前本校
・EYE大阪本校
・難波駅前本校
<兵庫>
・神戸本校
<和歌山>
・和歌山駅前校【提携校】
中国・四国地区
<島根>
・松江殿町校【提携校】
<岡山>
・岡山本校
<広島>
・広島本校
<山口>
・山口本校
・岩国駅前校【提携校】
<香川>
・高松本校
<愛媛>
・松山本校
・新居浜駅前校【提携校】
九州・沖縄地区
<福岡>
・福岡本校
<長崎>
・佐世保駅前校【提携校】
・日野校【提携校】
・長崎駅前校【提携校】
<鹿児島>
・鹿児島中央駅前校【提携校】
<沖縄>
・那覇本校
・沖縄プラザハウス校【提携校】
「資格の学校TAC」の教室講座の開講場所
「資格の大原」の教室講座の開講場所
北海道・東北地区
札幌校・函館校・盛岡校・仙台校
関東・信越地区
東京水道橋校・池袋校・早稲田校・新宿校・飯田橋校・町田校・立川校・中大駅前校・横浜校・相模大野教室・日吉校・千葉校・津田沼校・柏校・水戸校・大宮校・草加教室・宇都宮校・高崎高・新潟校・長野校・松本校
東海・北陸地区
富山校・金沢校・福井校・名古屋校・津校・岐阜校・浜松校・静岡校・沼津校
関西・四国地区
大阪校(新大阪)・難波校・梅田校・梅田校ライセンススクエア・神戸校・京都校・和歌山校・姫路校・愛媛校
九州・沖縄地区
福岡校・小倉校・大分校・宮崎校・沖縄校
「資格スクール大栄」の教室講座の開講場所
・青森県 (弘前教室・青森教室)
・岩手県(盛岡校・一関花泉教室)
・宮城県(仙台駅前校泉中央校)
・福島県(福島校・イオンタウン郡山校)
・新潟県(新潟校・長岡駅前教室)
・富山県(富山掛尾教室)
・石川県(かほく教室)
・福井県(Lpa福井校)
・長野県(飯田上郷教・室諏訪高島教室・長野古牧教室)
・東京都(池袋校・渋谷校赤羽ビビオ校・イオン西新井校・新宿校・銀座校・錦糸町校・上野校・自由が丘校・五反田校・大井町校・JR蒲田駅前教室・JR巣鴨・駅前教室・亀有教室・立川校・町田校・調布校・吉祥寺駅前校・八王子東急スクエア校)
・茨城県(水戸教室)
・栃木県(宇都宮ベルモール校)
・群馬県(前橋教室)
・埼玉県(熊谷校・所沢校・川越モディ校・浦和パルコ校・大宮アルシェ校・ララガーデン春日部校・せんげん台教室・上尾春日教室)
・千葉県(千葉駅前校・柏駅前校・津田沼校・新鎌ヶ谷アクロスモール教室)
・神奈川県(横浜校イオン海老名校・日吉東急校・上大岡校溝の口校・新百合ヶ丘校・藤沢校・川崎ルフロン校・秦野鶴巻温泉教室・川崎宮前平教室・平塚駅・前教室・横須賀教室)
・静岡県(静岡モディ校・プレ葉ウォーク浜北校・サントムーン柿田川校)
・愛知県(名古屋駅前校・金山校・テックランド星ヶ丘校・トヨタ校・東岡崎校・イオン豊橋南校・エアポートウォーク名古屋校・イオンモール扶桑校)
・岐阜県(マーゴ関校・アクアウォーク大垣校・マーサ21校)
・三重県(イオンモール鈴鹿校)
・京都府(京都駅前校北大路ビブレ校)
・滋賀県(イオンモール草津校)
・大阪府(梅田校・なんば校・枚方校・イオンモール茨木校・京橋校・あべのキューズモール校・千里中央校・河内長野教室・寝屋川教室・布施教室)
・奈良県(イオンモール橿原校・イオンモール大和郡山校・奈良田原本教室)
・和歌山県(橋本教室・有田教室・和歌山教室)
・兵庫県(三ノ宮校・イオン三田ウッディタウン校・川西校・姫路校・尼崎つかしん校・西宮北口校・明石校・加東教室・三木教室・鈴蘭台駅前教室)
・広島県(広島紙屋町校・広島大手町校・福山校・ゆめタウン呉校・アルパーク校・東広島教室)
・岡山県(岡山駅前校・イオンモール倉敷校)
・山口県(宇部教室)
・香川県(イオンモールマリタイムプラザ高松校)
・徳島県(徳島校)
・高知県(高知校)
・愛媛県(松山校)
・福岡県(福岡天神校・博多校・久留米校・小倉校・甘木駅前(朝倉)教室)
・佐賀県(佐賀校)
・長崎県(長崎校・島原教室・佐世保教室・諫早教室)
・大分県(アミュプラザおおいた校・別府駅前教室・大分県南教室・トキハ別府教室)
・熊本県(熊本校・人吉教室・八代教室)
・宮崎県(延岡教室・都城教室)
・鹿児島県(鹿児島校鹿屋教室・枕崎教室)
・沖縄県(沖縄那覇校・沖縄中部教室・沖縄北部教室)
パンフレット請求等一覧
オンラインWeb通信教育・独学向きの学校のパンフレット請求等