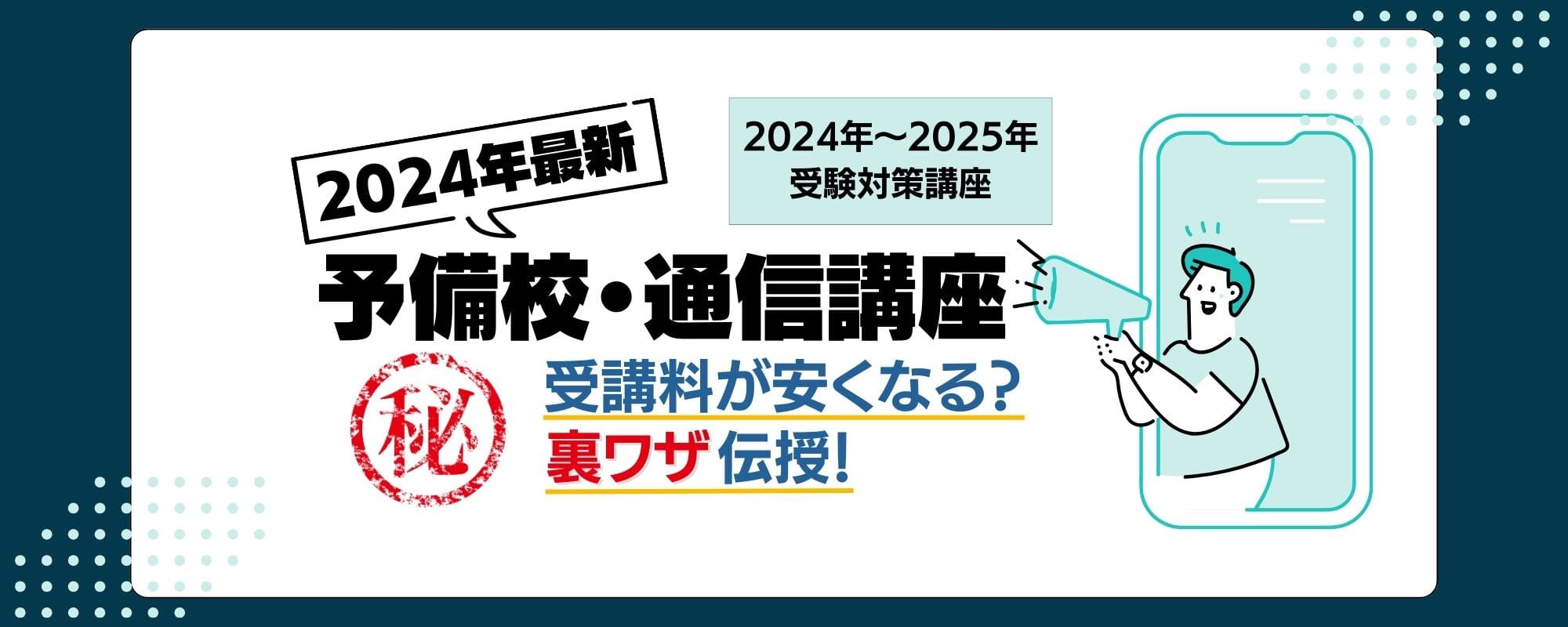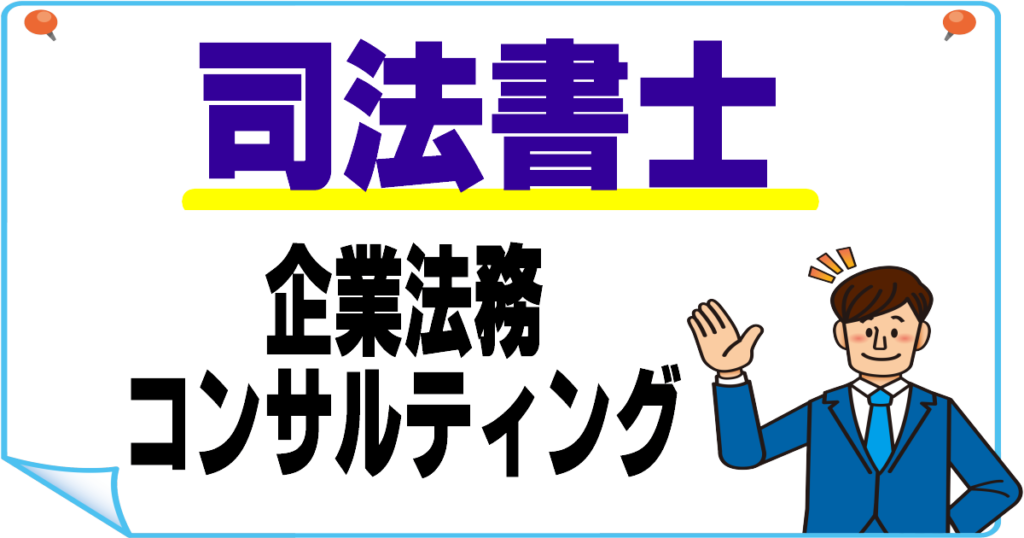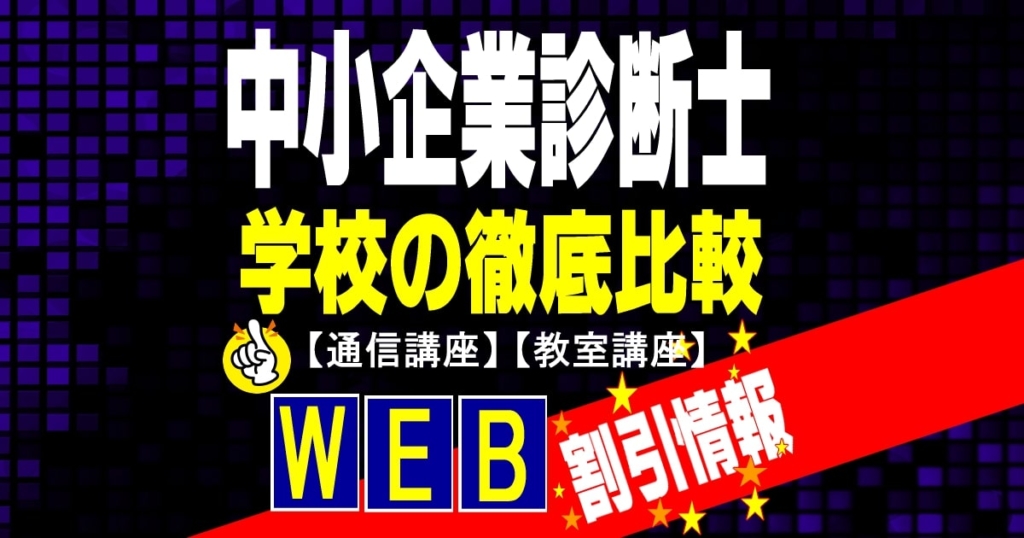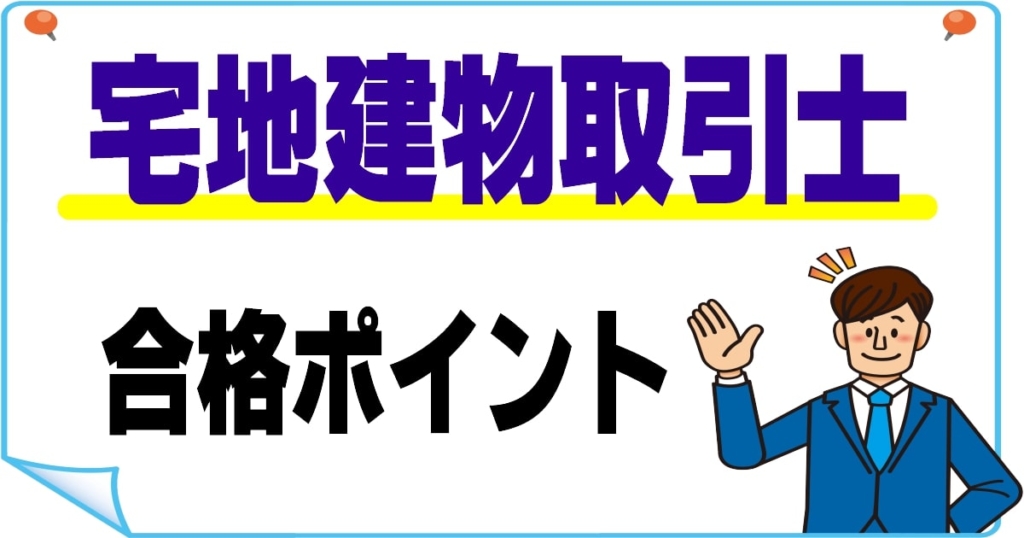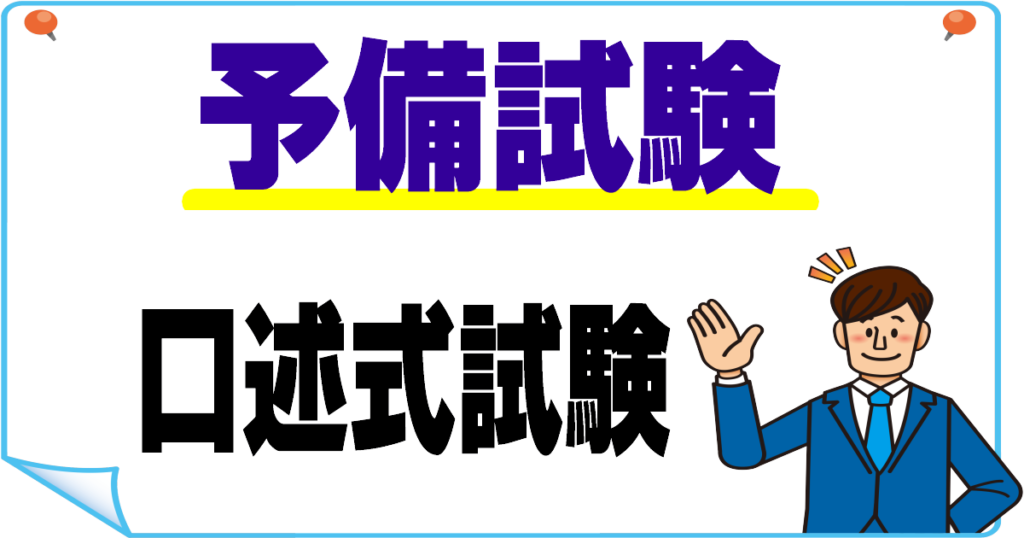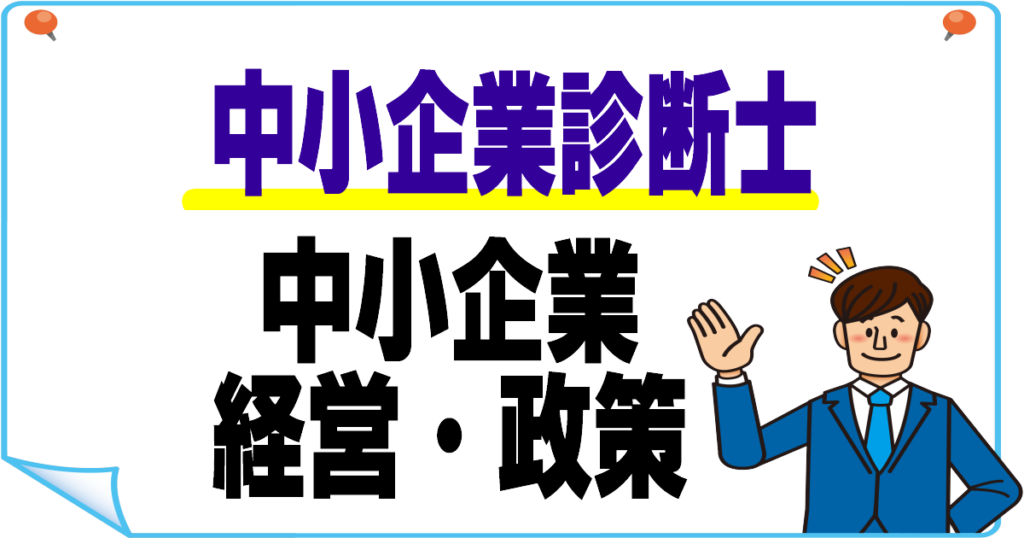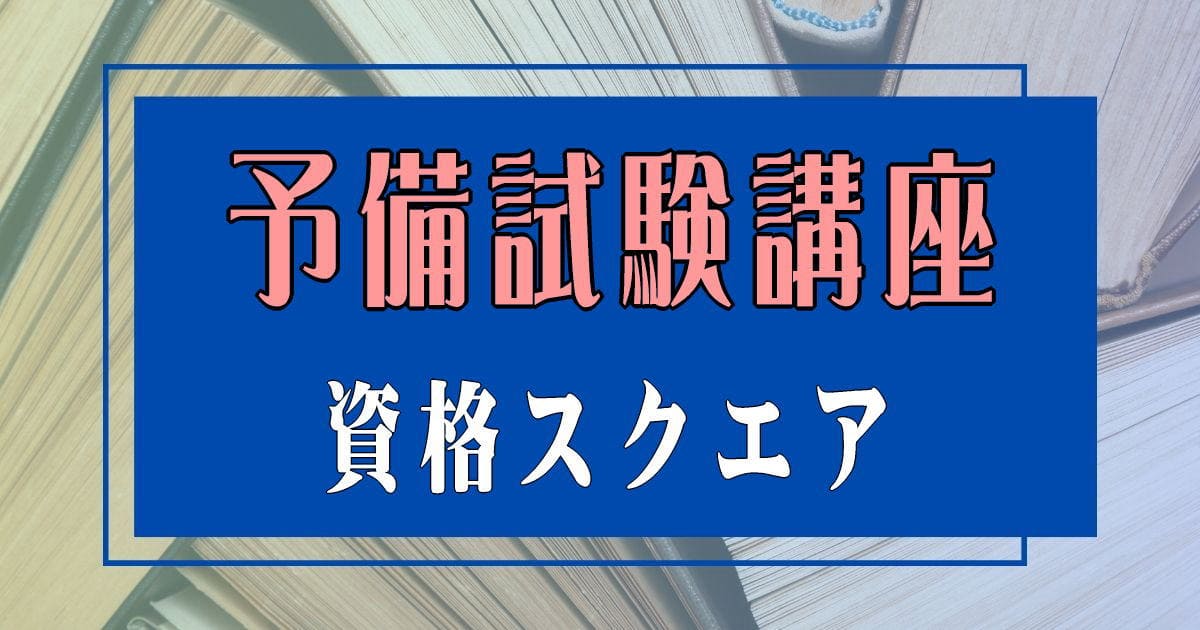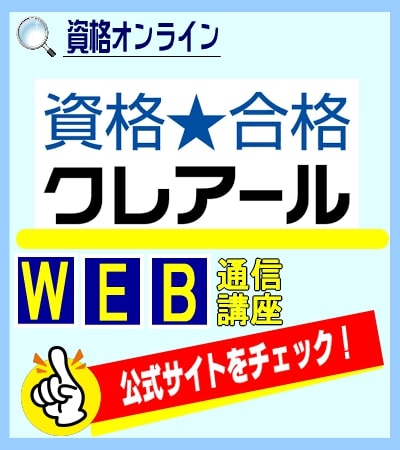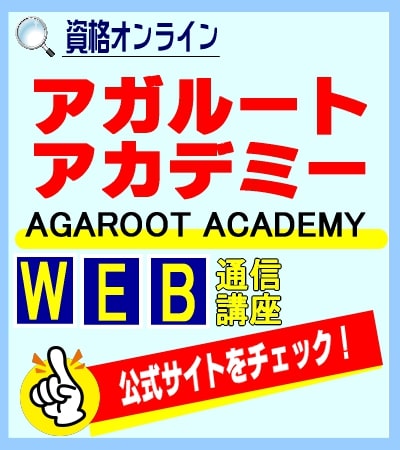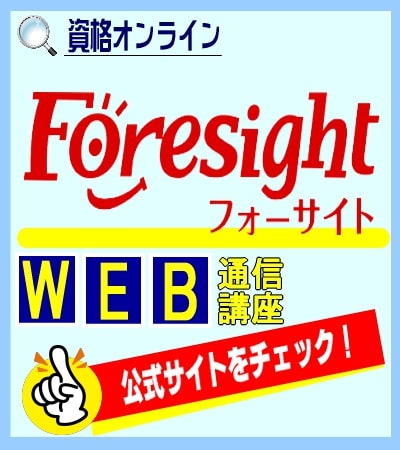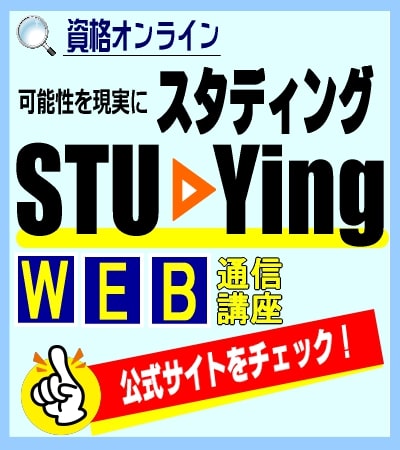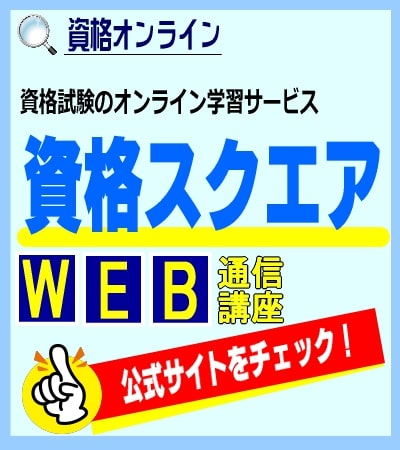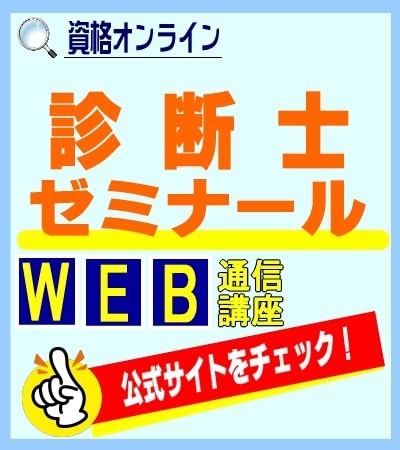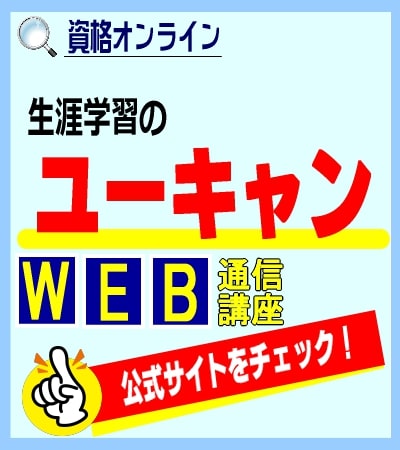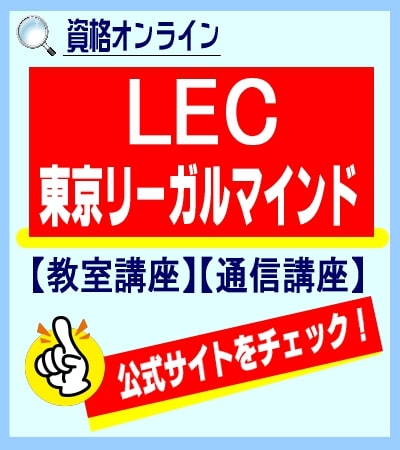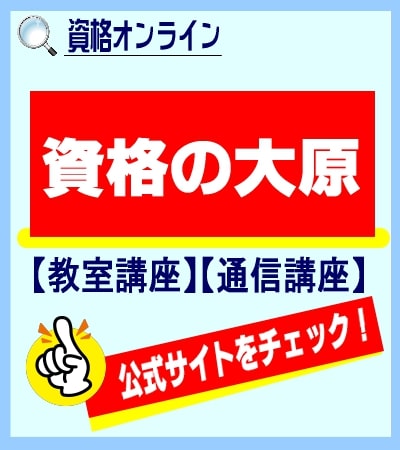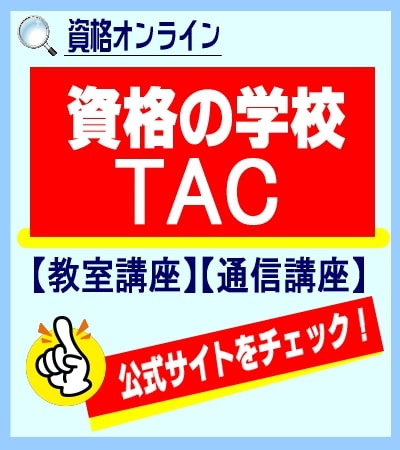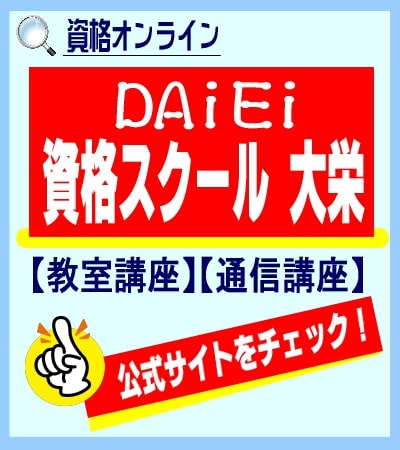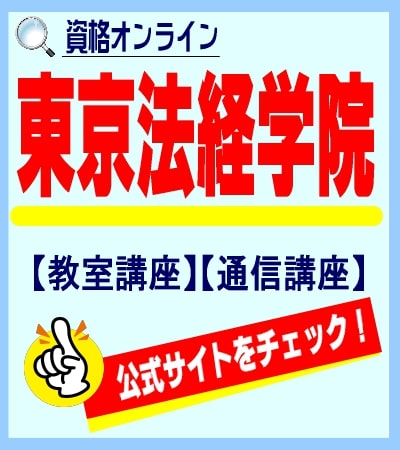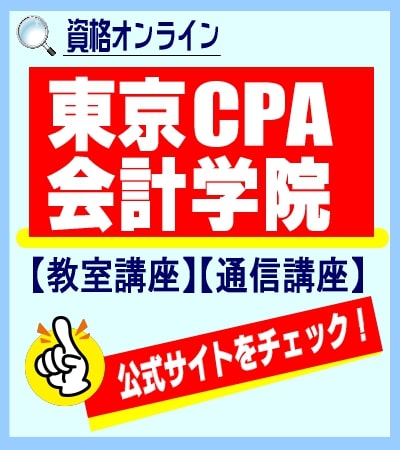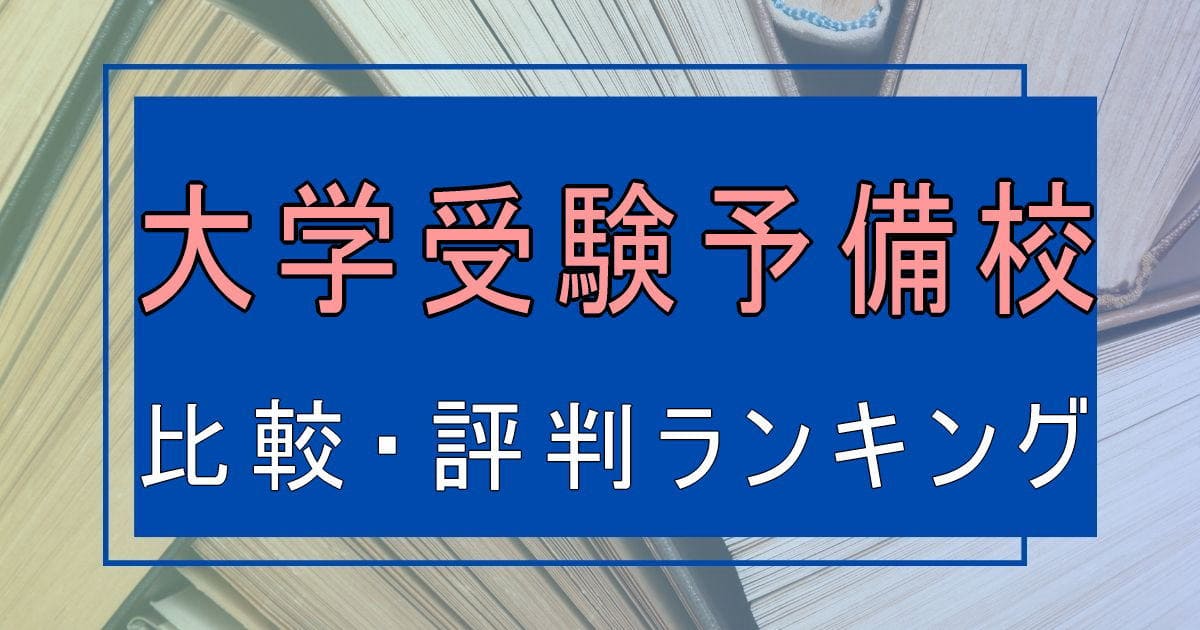当ページのリンクには広告が含まれています。
資格試験の予備校・通信講座のおすすめランキング|徹底比較【2024】評判・口コミ情報なら予備校比較のclover
当サイトでは、資格試験を受験する際の通信講座や通学講座の予備校・学校の情報や、各資格の勉強方法、費用について詳しく紹介します。
通信講座・通学講座・独学など、学習方法別におすすめの予備校・学校を紹介していますので、参考となれば幸いです。
資格試験の比較情報


「予備校比較のclover」をご覧いただきありがとうございます。
ご自身に合った学校を比較・選定される際の参考となれば幸いです。
資格試験を受験するに当たって、通信講座も通学講座も学校(受験予備校)の選定がスタートとなります。
予備校を選ぶことは、テキスト・先生とも合格するまで付き合うこととなります。
慎重におすすめの予備校を比較・検討することが大切です。
資格試験等の種類
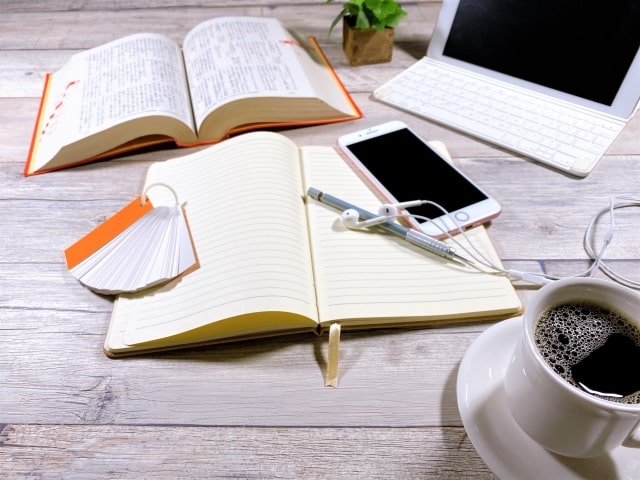
就職や転職に有利な資格試験、将来開業独立をしたい人向けの資格試験など人気の資格試験を掲載しています。
資格試験の日程、学習期間の目安、難易度ランキングの一覧は下記に掲載しています。
詳細は、各資格をクリックしてご覧いただけます。
会計・経営関係の資格試験
労務関係の資格試験
法律関係の資格試験
金融関係の資格試験
- FP1級・2級・3級(ファイナンシャル・プランナー)
- アクチュアリー
- 貸金業務取扱主任者
不動産・建築関係の資格試験
医療関係の資格試験
保育・介護関係
IT関係
その他
予備校・学校選びのポイント
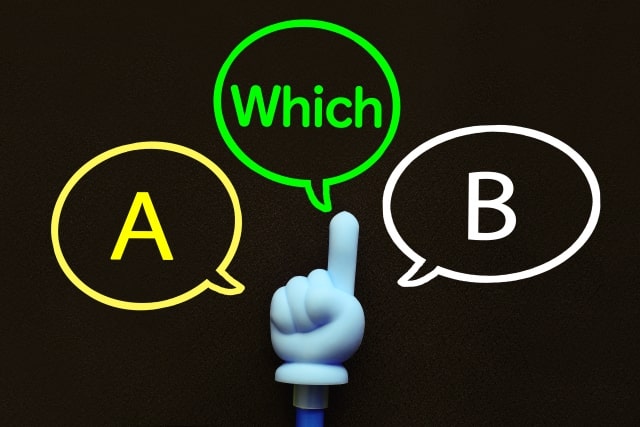
資格試験の合格に向けて勉強するための予備校・学校は、いくつもあります。通信講座や通学講座など種類も様々なので、自分にとって最も適した学校を選ぶと良いでしょう。
しかし、資格試験通信講座の予備校・学校はいくつもあるので、選ぶだけでも大変です。
資料を取り寄せたりネットで調べたりしながら比較していると、どれも同じように感じてしまうかもしれません。
資格試験に早く合格するためには最適な通信講座の予備校・学校選びがポイントとなってきます。
- 高い指導力・講師の質
常に最高の指導が受けられる力のある学校か。講師の質は高いか。 - 試験傾向に沿った最新の教材
合格のノウハウが詰まった良い教材が使われているか。 - サポート体制
入学から合格までサポートがしっかりしているか。 - 自分のレベルの把握
受験生の中での自分の実力が把握できるか。(受講者数が多い学校か。)
高い指導力・講師の質
授業内容も重要なポイントですが、講師も同じぐらい大切です。どれだけ高度な知識を教えてくれても、講師がわかりやすく指導しないと理解できません。
授業内容を消化しきれずに、せっかく習った知識が身につかなくなります。
良い講師なら、難しい内容も丁寧に指導するので、授業を聞いてればすぐに理解できます。講師の質で知識が身につくか決まると言っても過言ではないので、重要なポイントです。
教室講座がある学校で無料の体験がある場合は、それに出席して確かめることができます。
試験傾向に沿った最新の教材
卒業生や在校生からの評判で一番注意しておきたいポイントは、2021年最新の教材・授業についてです。
テキストや問題集が最新でなく、授業内容が低レベルすぎると、試験に合格するのは難しくなります。
授業で使用する教材、通信教育なら授業の形式(DVD、スマホ、タブレット等のオンライン講座)など、様々なポイントを比較しながら、確実に知識が身につくか判断しましょう。
サポート体制
さらに生徒へのサポート体制も、選ぶときには考えておかなければいけません。サポート体制が万全でないと、わからないところを質問することができません。これでは疑問点を解決できませんし、自分で解決しようとして、間違った知識を身につけてしまうこともあります。
特に、基本的に講師と顔を合わせることがない通信教育だと、いつでも質問できる体制は重要です。
サポート体制も万全なら、授業で疑問に思っても、すぐに解決することができるでしょう。
社会人向け資格

資格の中には、働きながらでも比較的受かりやすい資格や学業に専念しないと難しい資格があります。
仕事に忙しい社会人が自らの努力だけで資格試験の合格を得るには高いハードルがあります。
学習時間の確保だけでなく、受験仲間の存在も大きいと言えるでしょう。
そのために、最適な学校を探して効率よく勉強することが合格への第一歩となります。
学校へ行けないというリスクを減らすために通信講座が開講されている学校を選択することがおすすめです。資格試験合格のために自分にあった予備校・学校を探して、最小の学習時間で最大の学習効果を得ることで短期合格を目指しましょう!
資格試験合格のポイント
- 正答率の高い問題を落とさない!
どの資格試験についてもいえることですが、試験に合格するためには、正答率の低い問題を解けるようになるのではなく、他の受験生が落とさない問題を確実に解答できる力をつけることが肝心です。そのためには、まず基本的な理解を徹底的に深めることが必要です。
最終的には本試験レベルの問題が解ける解法と知識を学び、制限時間内に正解を導き出す技術を学校で学ぶことが、合否の可能性を飛躍的に高めることになります。 - 苦手分野を作らない!
どの資格試験も試験によって難易度が変わることがあります。苦手分野を作ってしまうと、試験の合格が遠のいてしまいます。どの分野もしっかりと試験対策を行うことが資格試験を短期間で合格するためには非常に重要です。
人気の資格試験
社会人又は学生に人気の試験は次の通りです。
- ★★★★★
税理士、司法書士 - ★★★★
中小企業診断士 - ★★★
社会保険労務士(社労士)、宅地建物取引士、日商簿記検定1級 - ★★
行政書士 - ★
日商簿記検定2.3級
※★の数は難易度の目安を表しています。
日商簿記検定試験は難易度により級があり、経理の資格として特に人気があります。
高校生・大学生・社会人向けの受験予備校

高校生・大学生・社会人向けの受験予備校・学校の情報を集めました。
安定志向の人におすすめの「公務員試験」対策講座が開講されています。
【公式】予備校比較のclover-YouTubeチャンネル
【公式】予備校比較のclover-YouTubeチャンネルでは、資格試験の勉強の仕方のほか、資格取得後に実務家がどのように仕事しているかなど生の声をお届けしております。
「予備校比較のclover」について
「予備校比較のclover」のサイトをご覧いただきありがとうございます。難関試験といわれる士業の資格取得までの勉強の経験、独立開業に至るまでの経験などを踏まえて資格試験の情報を提供しています。
「資格試験サイト」をご覧の皆様から、就職・転職の情報をサポートしてほしいとの要望が多く、「就職・転職情報」の関連サイト運営もしております。詳細は、「就職・転職サイト」をご覧ください。 当サイトをご覧になられた皆様の試験に合格し、希望の仕事が見つかりますことを心よりお祈り申し上げます。
通信講座の予備校・学校の選び方
2024年(令和6年)・2025年(令和7年)合格目標コースが登場!
自分にあったベストスクールを見つけることが資格試験合格への近道です。おすすめの通信講座の予備校・学校の情報を比較し、評判・人気をチェックしましょう!
費用を安く抑えるために独学による資格取得を目指している人は、オンライン通信専門スクール「アガルート」「スタディング」「フォーサイト」「クレアール」「資格スクエア」がおすすめです。
通信講座の予備校・学校の選び方独学におすすめのテキストと勉強方法
通学する時間や費用に問題がある人におすすめの独学による勉強方法は、「アガルート」「スタディング」「フォーサイト」「クレアール」「資格スクエア」の利用です。オンライン通信講座に特化することで他校に圧倒的な差をつけた価格設定になっています。また、テキストだけでなく、パソコンやスマホなどでWeb講義も見られますので、他の独学生に差をつけられる勉強方法になります。
新型コロナウイルスによる影響
2020年4月8日以降の緊急事態宣言を受け、一時期各資格試験が延期・中止となり、4~6月の試験が概ね8月以降に延期となりました。その後の各資格試験は徐々に通常通りの実施となってきました。
試験が延期等になったことは勉強を頑張ってきた受験生にとって非常に残念なことではありますが、勉強時間が増えたことを前向きに考えるほかありません。
2024年時点の資格試験については、概ね通常に戻っていますが、各資格試験に関する各団体の受験案内・ホームページ等で日程のご確認をお願いいたします。
一日も早く新型コロナウイルスが終息することをお祈り申し上げます。
災害時における資格の重要性
東日本大震災、リーマンショック、新型コロナウイルス・・・この10年の間に複数回の大変な危機が訪れています。その度に「手に職を」ということで資格試験が注目されています。
2020年~2022年は新型コロナウイルスにより経済活動に大きなダメージを受け、また、終息時期がわからない中において多くの業種が不安を抱えています。仕事が少なくなり、テレワークにより自宅滞在時間が増える中、資格の勉強をしようと前向きな人も多くいます。
2020年以降しばらくの間、新型コロナウイルスの影響により通学の資格の学校は一時休校となり、通信講座に切り替えられました。接触を避けるためにも通信講座に特化した学校にますます注目が集まっています。
新着記事・更新記事
-

予備校ランキング|おすすめの大学受験予備校の比較ランキング(費用・評判・勉強法)
-


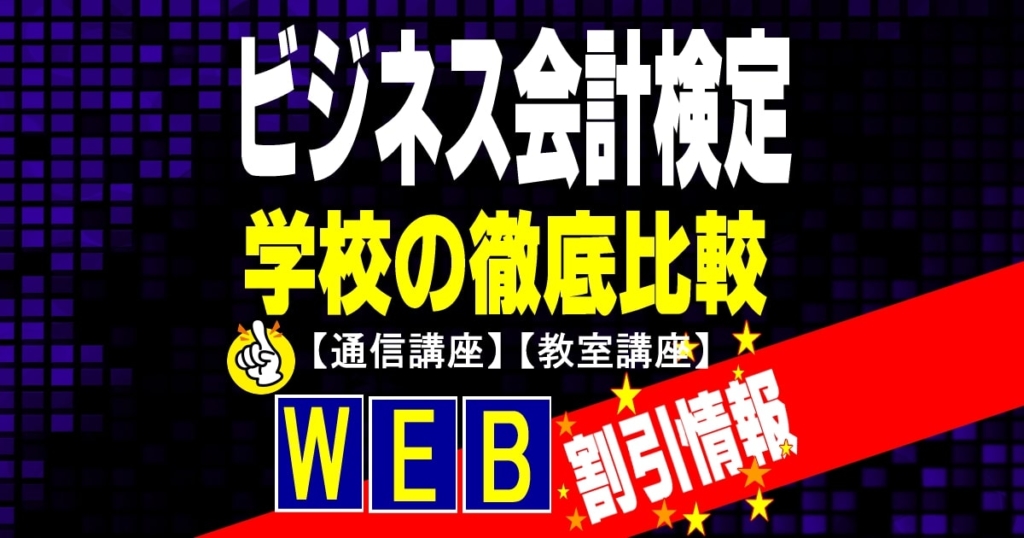
ビジネス会計検定試験の予備校・通信講座おすすめ!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


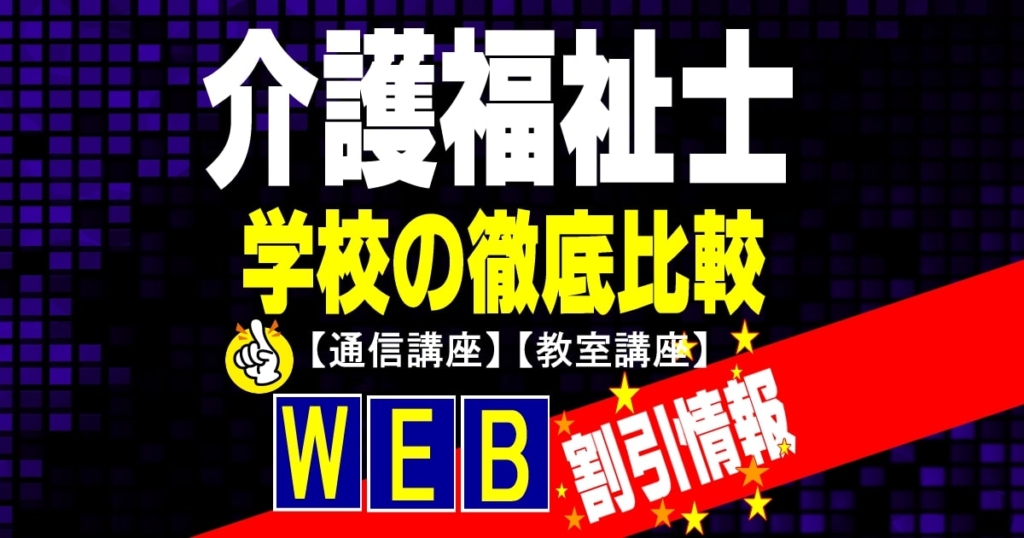
介護福祉士の予備校・通信講座おすすめ!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


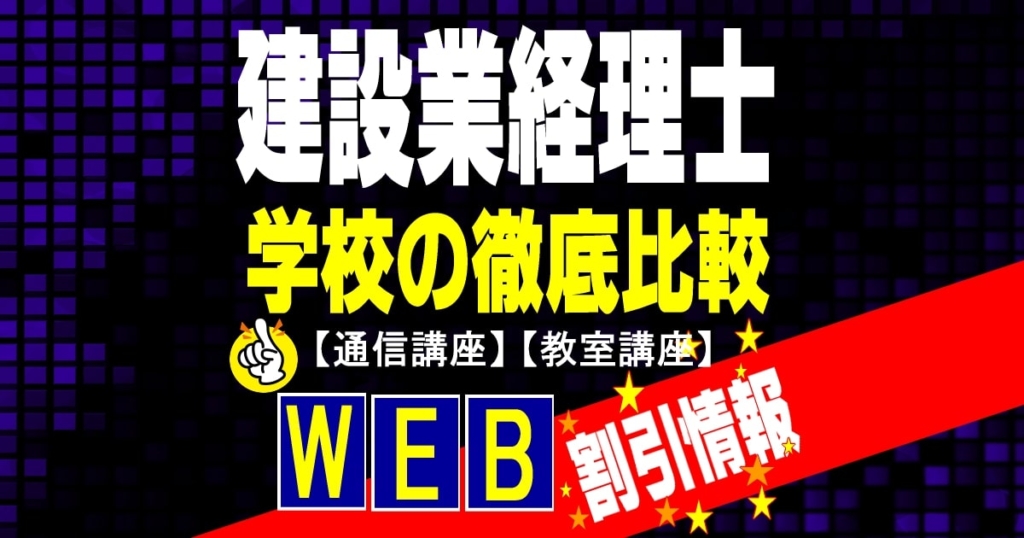
建設業経理士の予備校・通信講座おすすめランキングTOP2!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


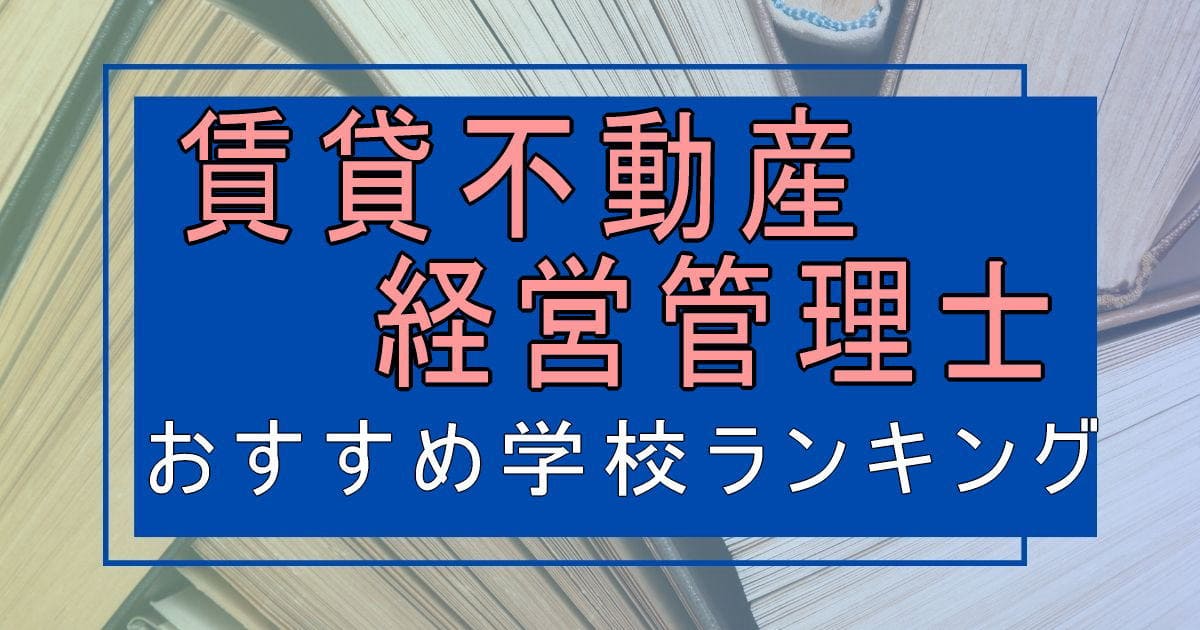
賃貸不動産経営管理士の予備校・通信講座おすすめ!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


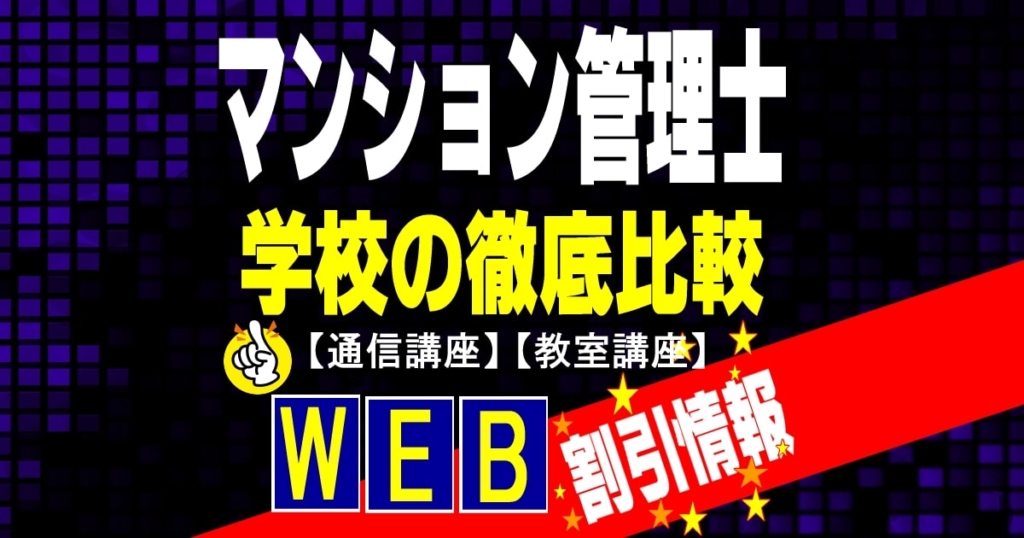
マンション管理士の予備校・通信講座おすすめランキングTOP2!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


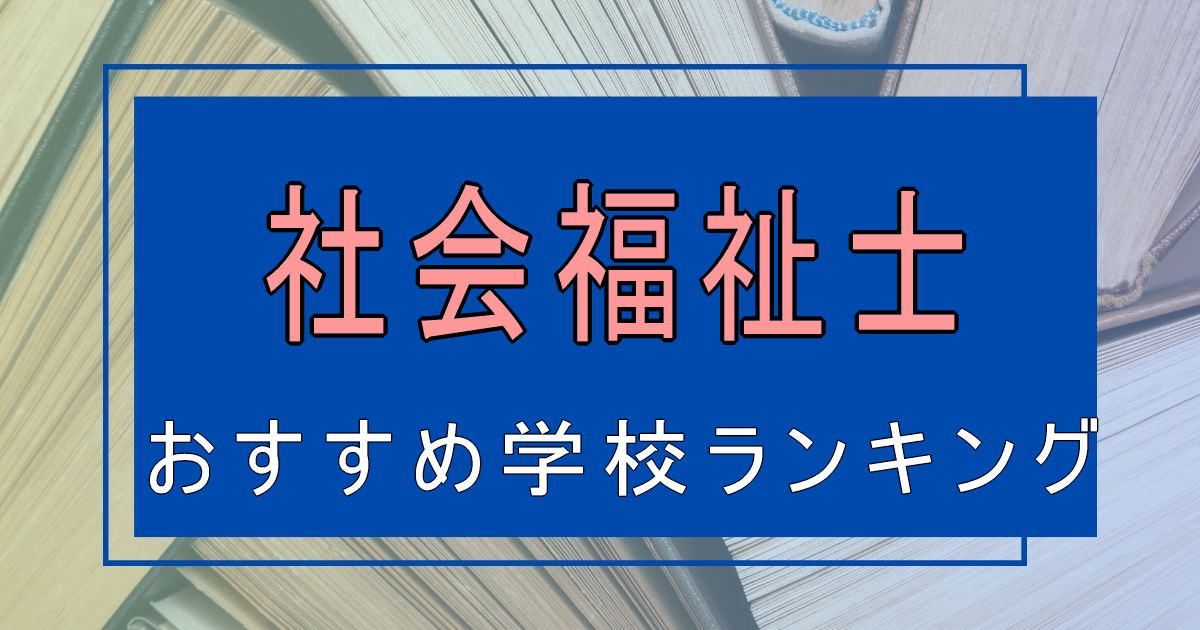
社会福祉士の予備校・通信講座おすすめ!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


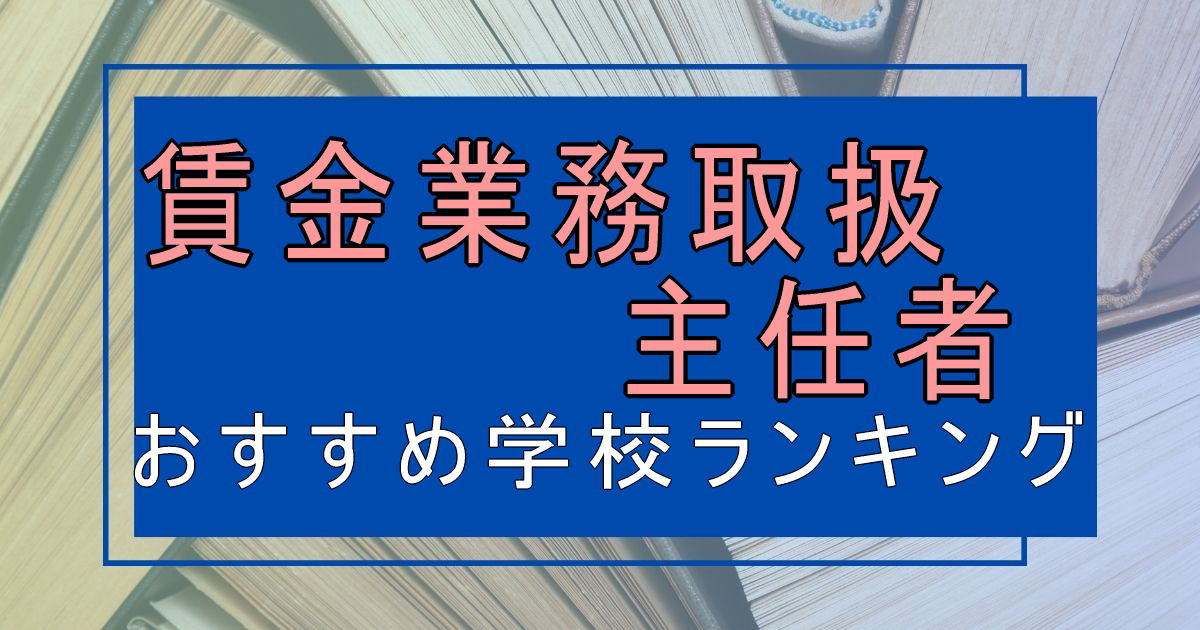
貸金業取扱主任者の予備校・通信講座おすすめランキングTOP3!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


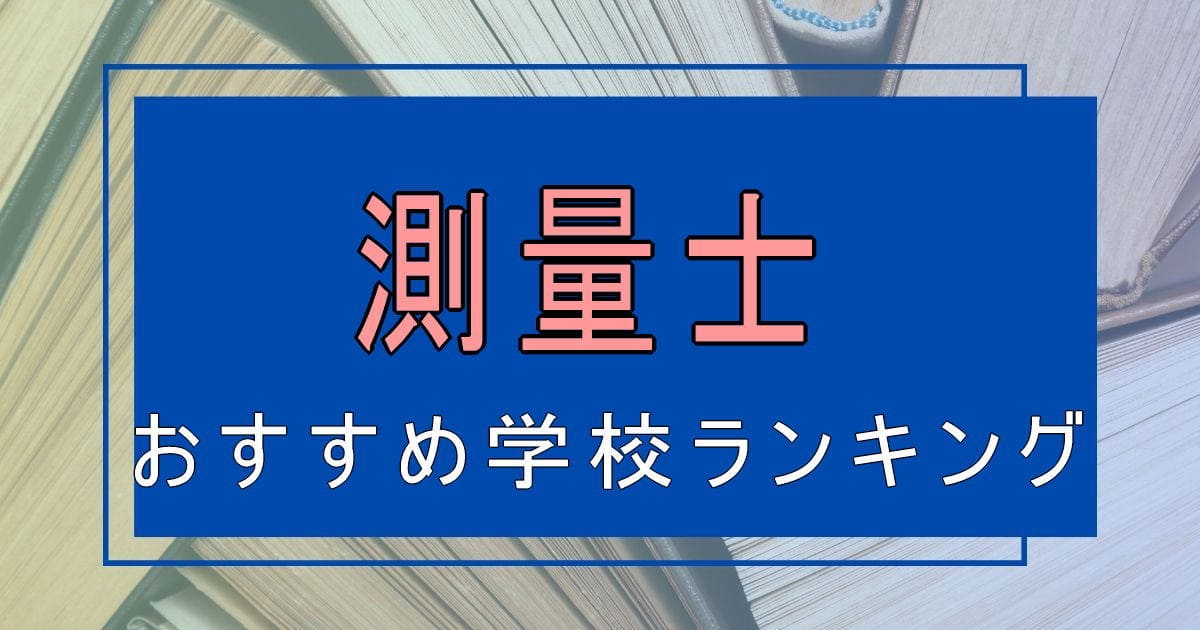
測量士の予備校・通信講座おすすめ!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


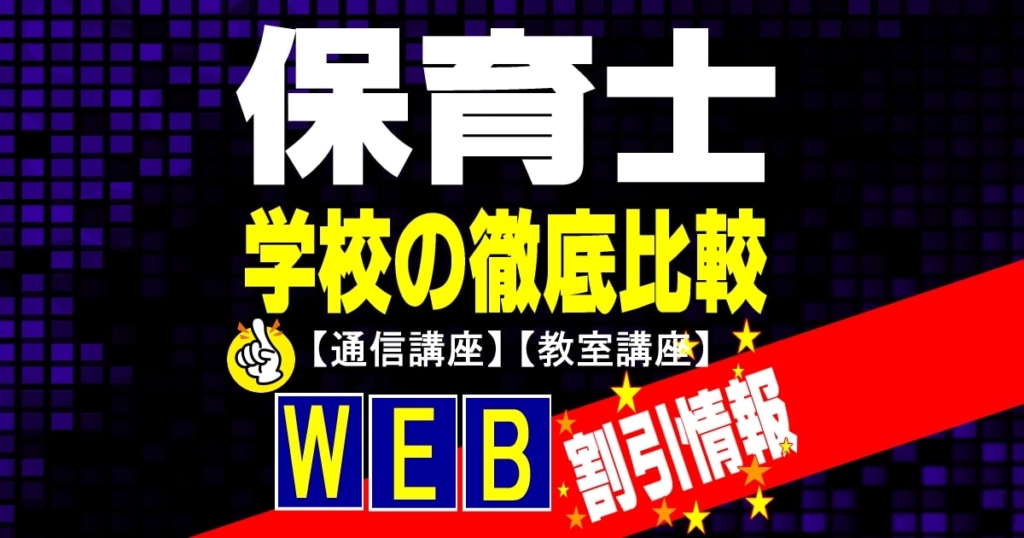
保育士の予備校・通信講座おすすめランキングTOP3!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


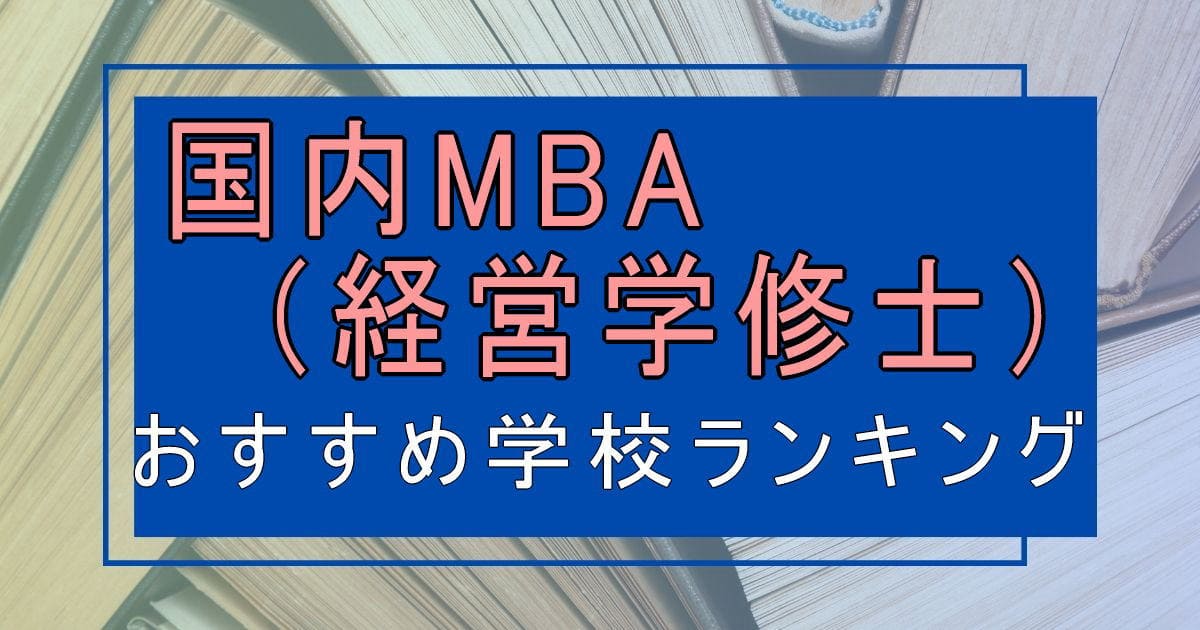
国内MBA(経営学修士)の予備校・通信講座おすすめランキングTOP3!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


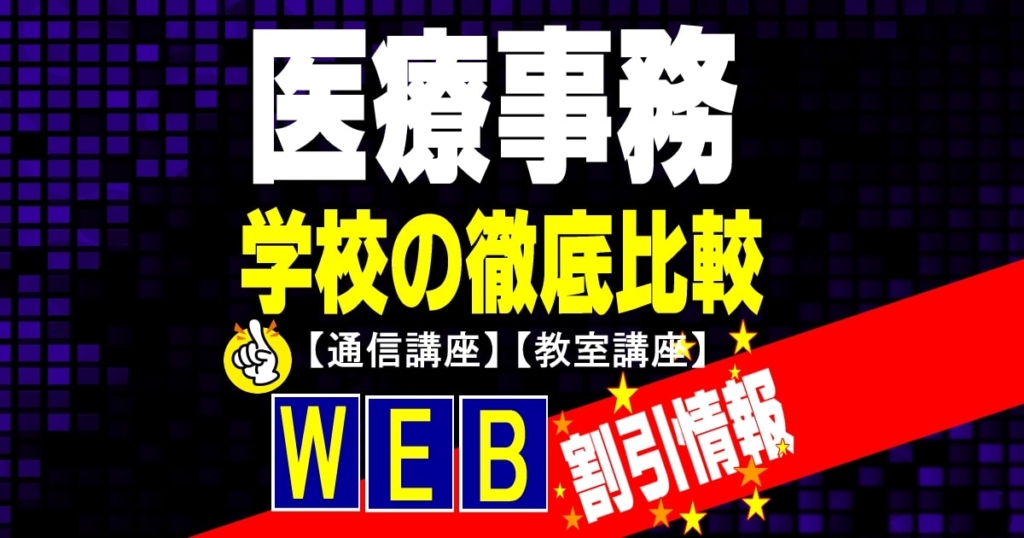
医療事務の予備校・通信講座おすすめランキングTOP5!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


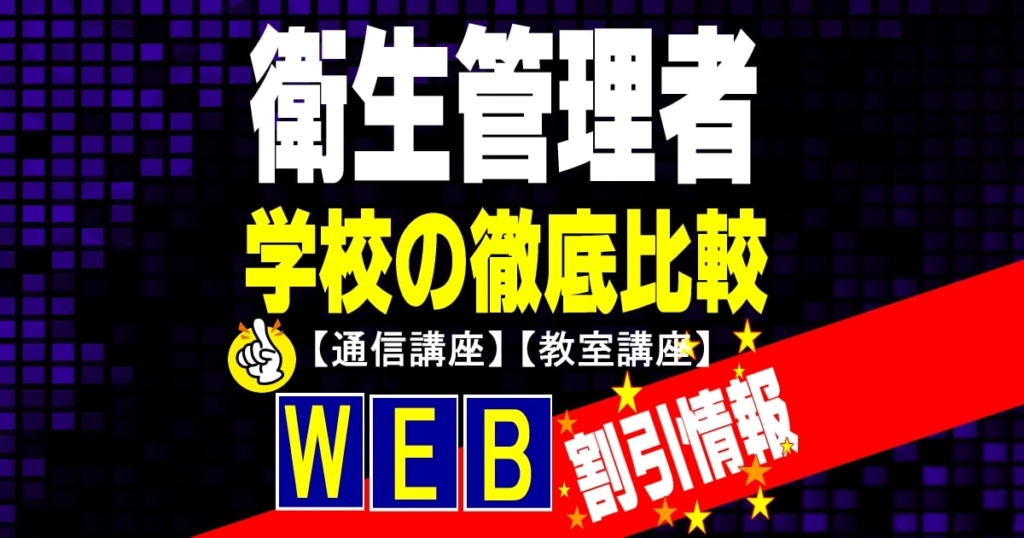
衛生管理者の予備校・通信講座おすすめランキングTOP3!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


/AI検定の勉強方法-1024x538.jpg)
G検定(ジェネラリスト検定)/AI検定の予備校・通信講座おすすめランキングTOP2!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


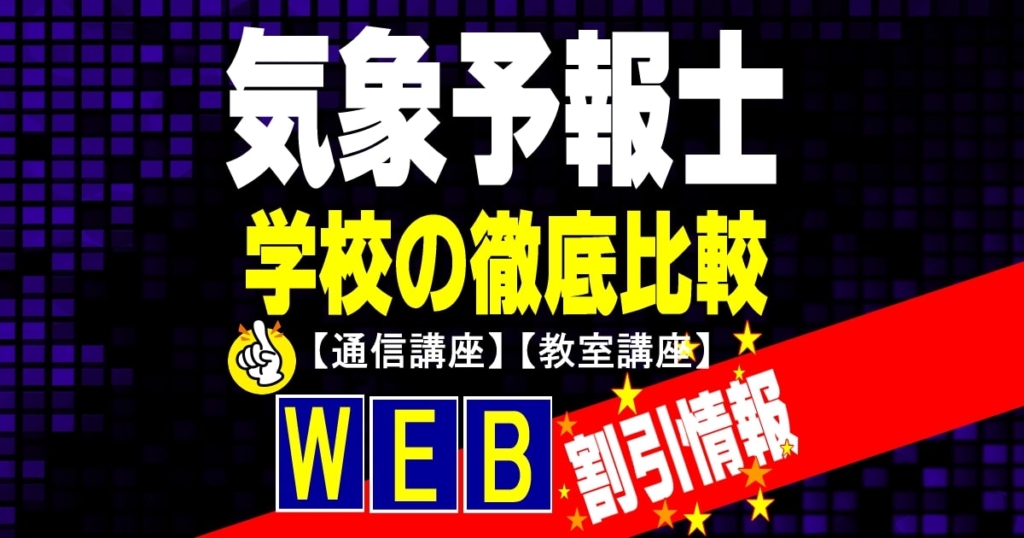
気象予報士の予備校・通信講座おすすめランキングTOP2!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


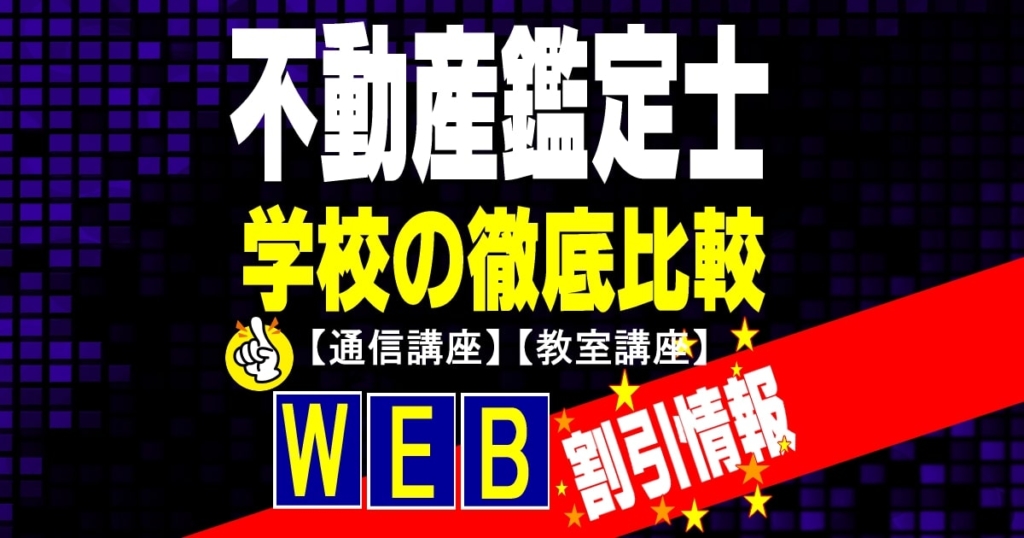
不動産鑑定士の予備校・通信講座おすすめランキングTOP8!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


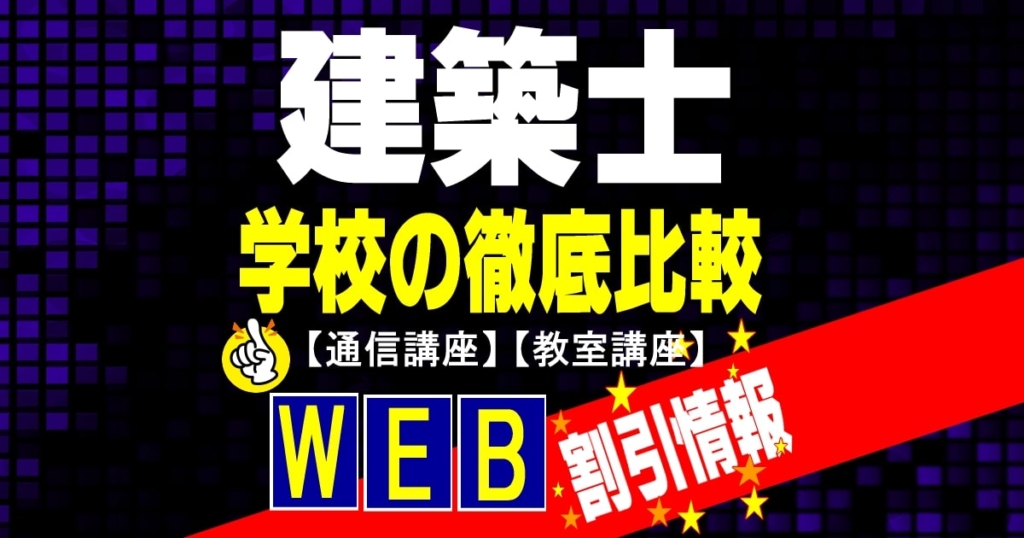
建築士の予備校・通信講座おすすめランキングTOP2!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


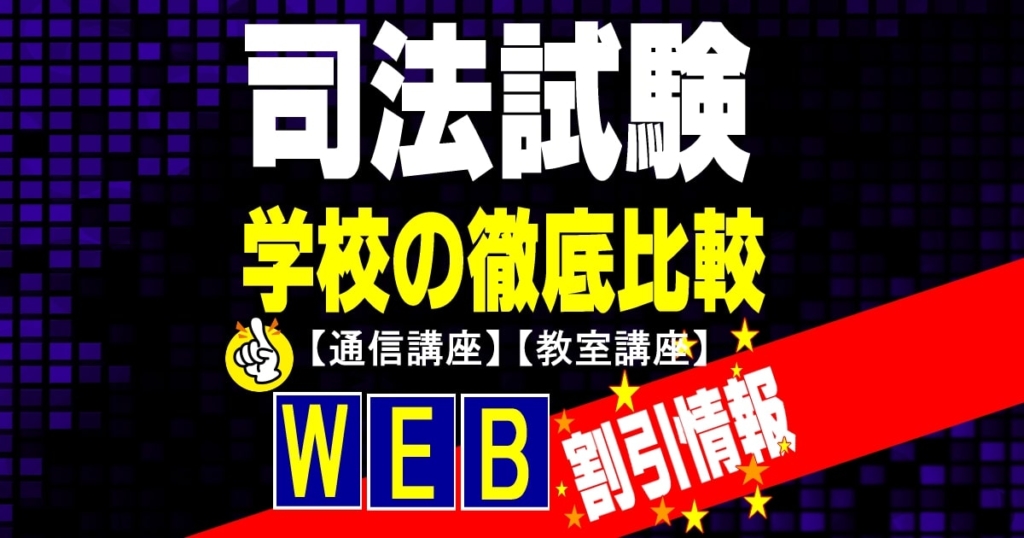
司法試験の予備校・通信講座おすすめランキングTOP5!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


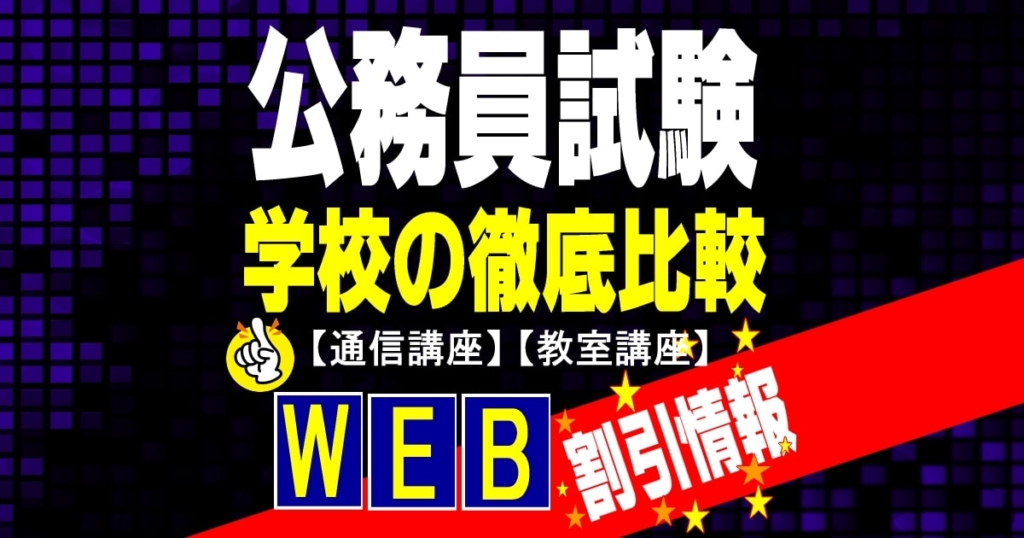
公務員試験の予備校・通信講座おすすめランキングTOP8!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


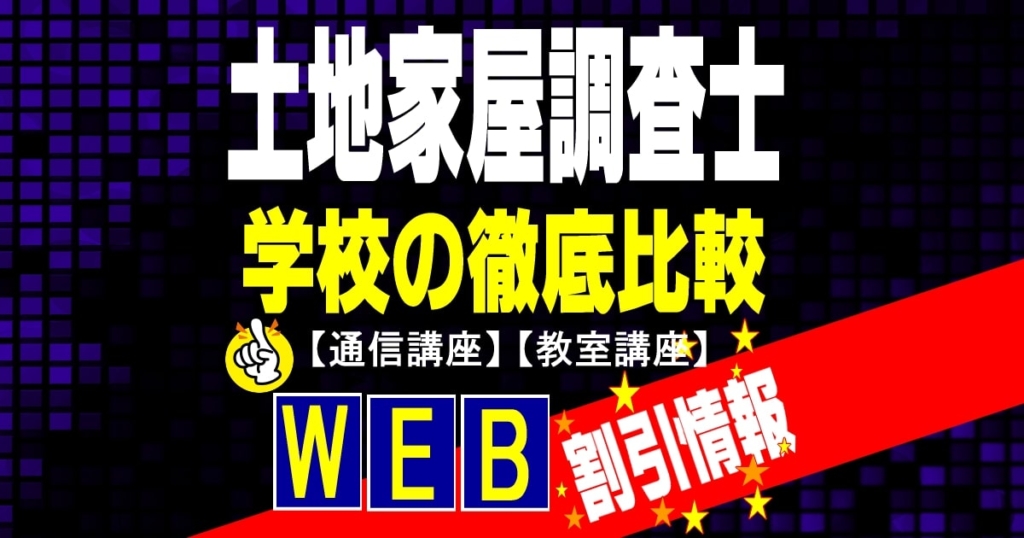
土地家屋調査士の予備校・通信講座おすすめランキングTOP3!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-



弁理士の予備校・通信講座おすすめランキングTOP5!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


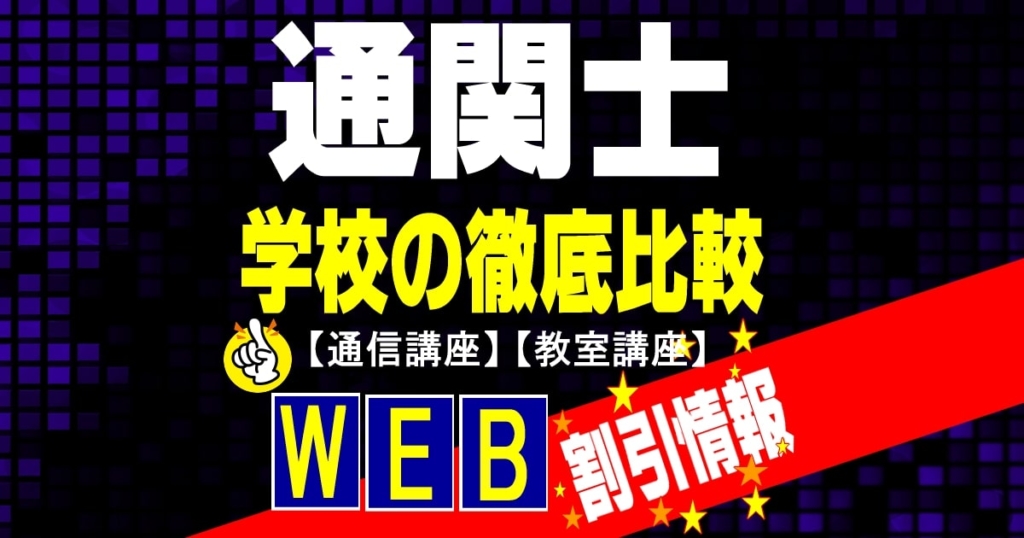
通関士の予備校・通信講座おすすめランキングTOP6!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-



FP(ファイナンシャルプランナー)の予備校・通信講座おすすめランキングTOP8!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】
-


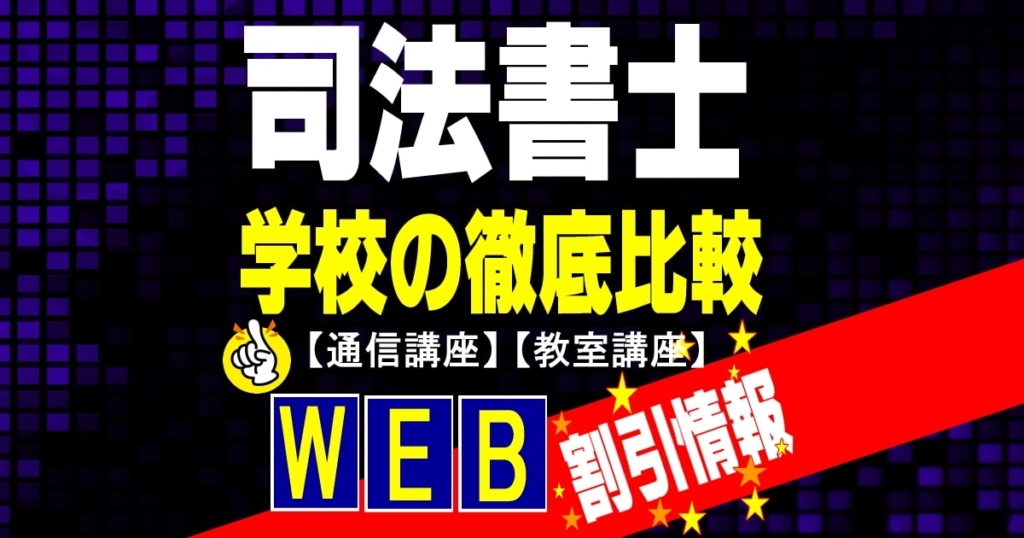
司法書士の予備校・通信講座おすすめランキングTOP8!費用や合格率を徹底比較【2024年最新】